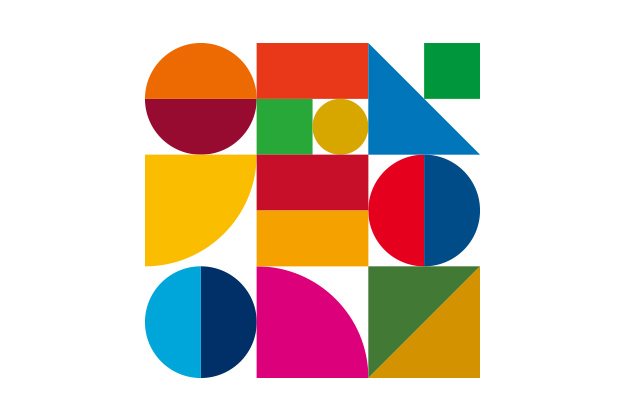ブランド価値が、企業価値を高める時代に
企業価値向上のために、SDGsブランディングにどう取り組むか
企業価値は、ブランドのマネジメント力に左右される
サステナビリティを追求する企業のトップとミーティングさせていただく際に、ここ1、2年で、企業ブランドを無形資産として重要視する発言が急速に増えてきていることを実感しています。また、ブランドに投資する必要性について、広報部門やマーケティング部門でなく、経営企画部門からお話を伺うケースもかなり増えてきています。企業において、ブランドが経営の中枢で語られている現状を踏まえて今日はお話しさせていただきたいのですが、そもそも「ブランド」の定義について改めて教えていただけますでしょうか。
一橋大学大学院経営管理研究科 教授
阿久津 聡氏
阿久津 ブランドの定義としては、「売り手が差別化を意図し、市場に提供している商品に付けた名前やロゴ、デザイン、もしくはそれらを組み合わせたもの」といったものが一般的です。ここでいう「商品」というのは広い意味で、市場にあるモノやサービス、企業組織やヒトも含みます。つまりブランドとは、それが指し示す商品を象徴する名前やロゴといった「記号」だと捉えることができます。そして、ブランドがもたらす価値の源泉は、市場参加者が持つ「その商品」についての「知識」なのです。
マーケティングの世界では早い時期からそうしたブランドから連想される知識が商品に与える価値に関心が向けられ、市場参加者をはじめとするブランドのステークホルダーが持つブランドに関する知識を効果的にマネジメントしていこうとする、いわゆるブランド・マネジメントが発展しました。
そうした前提を踏まえると、企業を指し示すいわゆる「企業ブランド」に、企業価値に影響を与えるほどの力があっても不思議ではないでしょう。企業は市場において常に評価にさらされます。評価の基になるのは、市場参加者が持っているその企業についての様々な知識です。企業が提供している商品を使ってみたり、CMを見たりして得られた知識が、「技術的に優れているという評価」や「洗練されているイメージ」という新たな知識を生み出し、それらの知識すべてが私たちの頭の中で企業ブランドから連想されるものとして整理されるわけです。高い評価や良い印象をもたらす知識がその企業ブランドに集約され、それを見たり聞いたりしたときの私たちの反応に影響するわけです。
その上で、経営において企業ブランドのマネジメントの重要性がいま一段と増しているのはどういった理由からなのでしょうか。
阿久津 そもそも企業価値の大きな割合を占める無形資産としてブランド価値が経営者の間で強く意識されるようになったのは、1980〜90年代の米国・欧州で大型のM&Aがあちこちで行われるようになったことがきっかけになったといわれています。企業を買収する際には、買収先の企業の価値をどう評価するかが問題になりますが、とりわけ経営者のマネジメント力に大きく左右されるブランド価値をどう評価するかが大きな問題になったわけです。逆に、買収される企業の立場に立てば、ブランド価値をどう評価させるかが大きな問題になったということです。
その頃、大手自動車メーカーのGMとコカ・コーラの時価総額がほぼ同じだったことがあり、話題になったといいます。土地や工場といった有形資産や従業員数で比べると、コカ・コーラはGMよりはるかに小さく、その価値の大部分はブランド価値が占めていました。そのため、企業価値の算出に際して、ブランド価値の評価がいかに重要かを知らしめたそうです。
一方、日本企業には古くから「のれん」という概念があって、企業ブランドの無形資産としての価値は認識されていたものと考えられています。ただ、戦略的にそこに投資をし、持続的なリターンを得ていくというマネジメントの発想はあまりなかったようです。
最近の企業ブランドのマネジメントに対する経営層の関心の高まりの背景には、いくつもの要因があるものと考えています。その中でもとりわけ、労働市場における人材獲得競争、製販両面での本格的な海外進出、経営者の世代交代による象徴の必要性、といったものの高まりが、企業ブランドへの戦略的な投資とマネジメントに対するニーズを高めているように思います。
SDGsを企業ブランディングの羅針盤にせよ
SDGsは企業ブランディングにどのような影響をもたらしているのでしょうか。
阿久津 現在は外部のステークホルダーが、企業の評価基準としてSDGsを一つのよりどころにしようとしている段階です。外からの評価は最初にお話しした通り、もともとブランド価値の源泉です。企業を取り巻く様々なステークホルダーがSDGsの取り組みを含めて企業を評価しようとする以上、企業はブランディングの中心にSDGsを据える必要が出てきます。
ここでいう企業ブランディングは、ブランドがもたらす価値を企業に付与していく活動を指します。そもそも企業ブランディングは中長期の視点で考えるべきテーマですが、新型コロナによって先行きが極度に不透明な状況になると、企業ブランドが企業の存続にも直結します。この企業の存在価値は何なのか、存続させたほうがいいのかどうかを外部が判断するようになるからです。
外部ステークホルダー、とりわけ顧客からの評価が、企業存続のために何よりも重要であることは、企業の存在理由であるミッションを中心とする企業理念を考える上で極めて重要です。今回のコロナ禍において、例えば以下のような話を何度となく聞かれた読者もおられるのではないでしょうか。
親子二代にわたって続いた老舗ラーメン店の経営がコロナの影響で厳しくなってきて、対応も大変だということで疲れた店主が閉店を決意したとします。それを常連客に告げたところ、「おやっさんが先代から受け継いできたこの味は絶対に絶やしてはいけない。自分たち常連客も応援するからぜひ店を続けてほしい」という声が起こり、クラウドファンディングで資金援助したり感染に気を付けながら積極的に来店したりした。店主は自分の使命と責任を感じて閉店を見送った。
こうした話は、常連客というステークホルダーに「絶やしてはいけない味」や「大切にしたい思い出」といった価値を認められ、事業の存続を果たした事例といえます。ラーメン店も企業も同じです。コロナ禍のような予想外の事態が生じて、企業が存続の危機に見舞われたとき、その運命を左右するのは常連客をはじめとするファン、外部の支援者の存在です。
地球環境やコミュニティのサステナビリティへの積極的な貢献を通じて、「無くなったら困る『なくてはならない』会社」という評価を、外部のステークホルダーから得ていれば、最終的には会社のサステナビリティにも貢献するのです。SDGsを経営のよりどころとして、実質的な活動を推進し、企業ブランドを通して自社の存在価値を内外のステークホルダーに示していく。こうした活動が企業自体の存続に直結することを感じた経営者が、今回のコロナ禍で増えてきたように思います。
企業価値を外に発信する前にすべきこと
ラーメン店のお話はとてもわかりやすく、共感します。企業がいくら自らの存在意義を声高に訴えたところで、ステークホルダーが評価しなかったら存続できない、というのはシビアな現実であり、だからこそ企業は、自らの存続をかけて企業ブランディングをしっかり行っていく必要があるのですね。
そうした企業ブランディングの重要なターゲットの一つとして若者も挙げられると思います。学習指導要領が改訂され、今年から小学校においてもSDGsの教育が一層進んでいますが、採用なども見据え、SDGsに慣れ親しんだ若者から共感される企業ブランドをつくるには、どのような施策が必要でしょうか。
阿久津 当たり前のことかも知れませんが、SDGsに慣れ親しんだ若い世代から共感される企業になるには、まずは真摯にSDGsに取り組んでいく必要があるだろうと思います。ただ、それだけでは十分でなく、それを若い人の目線でもわかりやすく伝えていく活動が必要になるのではないでしょうか。企業ブランドが象徴すべき企業理念がSDGsを踏まえたものであることはもちろんですが、それに既存の社員が共感共鳴していないことには新卒採用の面談などで就活生には伝わりません。
様々な企業のミッションステートメントを調査した研究によると、そこに書かれた文言は多くの企業で共通のものが多く、差別化は容易でないと分かっています。ともすると、どの会社のミッションステートメントも同じように見えてしまう。とはいえ、ブランドとはそもそも差別化を目指すものですから、ミッションの文言だけで他社とは違う「自社らしさ」を伝えられないようなら、ミッションの実践・実現方法などできちんと伝えていく必要があるでしょう。
私自身、企業のミッションステートメントの再策定を支援させていただく機会があります。しかし、他の企業に置き換えても通じてしまうのでは?というミッションステートメントがまだまだ多く存在していて、残念に思っています。
SDGsをよりどころとする企業ブランディングにおいて、従業員も重要なターゲットになるということですが、SDGsを従業員に浸透させるためのポイントがあれば教えてください。
阿久津 企業ブランディングにSDGsを絡めることの重要性をトップや推進部署が理解していても、社内浸透ができていない点を課題に挙げる企業は多く見られます。
ブランドを外部へ伝えるには、まず社員一人ひとりがブランドの象徴する理念を自分ごととして内在化していなければなりません。ですからトップの推進力でSDGsへの取り組みを始めた企業も、次のステージとして、社員がどれだけブランドの理念をSDGsと関連させて内在化しているかが評価ポイントになります。とはいえ、ごく普通の日本の会社員の方に「世界の貧困をなくそう」といきなり言っても、唐突過ぎて自分ごとにしてもらうのはなかなか難しいということも理解できます。
私は、一般的に企業が社員にSDGsを浸透させる際にまず重視すべきゴールは、8番の「働きがいも経済成長も」だと考えます。やはり個人にとって身近なインセンティブがなければ、社内浸透はなかなか進みません。社員一人ひとりが働くことにやりがいを感じ、生活や健康の維持向上につながると実感してはじめて、それが社内全体に浸透していくだろうと考えています。自分が携わる仕事が誰かのためになり、会社もその貢献にコミットしながら発展を目指しているということが実感できれば、他のゴールにも目が向きやすくなるのではないかと思うわけです。
SDGsブランディングとは、自社の理想の確立
今回のコロナ禍によって機関投資家も企業が従業員の健康や働きがいをどうマネジメントしていくかに注目していますね。
社内浸透のあり方も含め、阿久津先生が共感するSDGsブランディングの事例がありましたら教えてください。
阿久津 一社挙げさせていただくとすれば、エーザイさんでしょうか。患者さんの満足を増大させるという企業理念に本気でコミットしようという思いが定款にも込められ、真剣度にすごみがあります。組織体制としても知識経営論をベースにしっかりとした理念経営を実践されており、知識創造部という部門がステークホルダーに高い価値を提供していく仕組みができています。
同時に、個々人の実体験を重んじ、一定の時間を顧客すなわち患者さんと過ごすことがすべての社員に求められています。自社が創る薬を使う患者さんと喜怒哀楽を共にする体験を通じ、提供する価値の具現化を自分ごとにする取り組みとして推進されています。
エーザイさんはまさに、多様な無形資産を擁し、コーポレートサイトや統合報告書における情報開示においても際立っている印象です。最後に、SDGsをよりどころとしたブランドづくりに企業は今後どう取り組むべきか、アドバイスをお願いします。
阿久津 SDGsのゴールを一つ一つ順番に検討する入り方より、自社が実現したいと考える価値や未来はどんなものなのか、自社の理念としてのミッション(=自社の存在意義)、ビジョン(=将来ありたい姿)、バリューズ(=大切にしている価値観)を振り返るところから入ることを勧めます。それがSDGsのゴールとどのように関連するのか、関連性の高いゴールを取り上げて、それをどのように捉え、どのような取り組みが可能かを考えるほうがやりやすく、気持ちも入りやすいものと思います。
また、SDGsは外部のステークホルダーが世界共通の価値観として提示したものですから、独自性をもってそれを実践していくことが容易ではないことは明らかです。まずは社内で個々人が自分ゴトとして取り組み、やりがいや意義を感じられるかどうかが肝要です。次に、それが外部のステークホルダーから見ても高く評価し得るものであるかを確認・担保し、最後にそれをしっかり内外に伝えていく。外部から評価されていることが内部のやりがいや意義に影響を与えることも忘れてはなりません。この3つのプロセスで考えるのが分かりやすく、やりやすいのではないかと思います。
SDGsの情報開示は一歩間違うとSDGsウオッシュとしてブランドを損なうリスクもあり、おっしゃる通り自社が外からどう見られているかを把握することが重要だと考えます。
弊社が運営するブランド価値評価調査「ブランド・ジャパン」の企画委員会委員長を務めていただいている阿久津先生と私たちSDGsデザインセンターは、今後さらに連携し、SDGsをよりどころとする企業のブランド力向上を支援させていただきます。トップや経営企画部門の皆様からのご相談をお待ちしております。
阿久津先生、本日はありがとうございました。
サステナビリティ本部 本部長
古塚 浩一
2018年、日経BPコンサルティング SDGsデザインセンター長に就任。企業がSDGsにどのように取り組むべきかを示した行動指針「SDGコンパス」の5つのステップに沿って、サステナビリティ経営の推進を支援。パーパスの策定やマテリアリティ特定、価値創造ストーリーの策定から、統合報告書やサステナビリティサイト、ブランディング動画等の開示情報をつくるパートまで、一気通貫でアドバイザリーを行うことを強みとしている。2022年1月よりQUICK社とESGアドバイザリー・サービスの共同事業を開始。ESG評価を向上させるサービスにも注力している。
阿久津 聡(あくつ・さとし) 氏
カリフォルニア大学バークレー校Ph.D.(経営学博士)。専門はマーケティング、消費者行動論、ブランド論。
著作に『ブランド戦略シナリオ - コンテクスト・ブランディング』(ダイヤモンド社:共著)、『ソーシャルエコノミー』(翔泳社・共著)、『ブランド論』、『ストーリーの力で伝えるブランド』(ダイヤモンド社:訳書)、『カテゴリー・ イノベーション』(日本経済新聞出版社:監訳書)、『弱くても稼げます』(光文社:共著)、『サクッとわかるビジネス教養 マーケティング』(新星出版社:監修)などがある。
※肩書きは記事公開時点のものです。