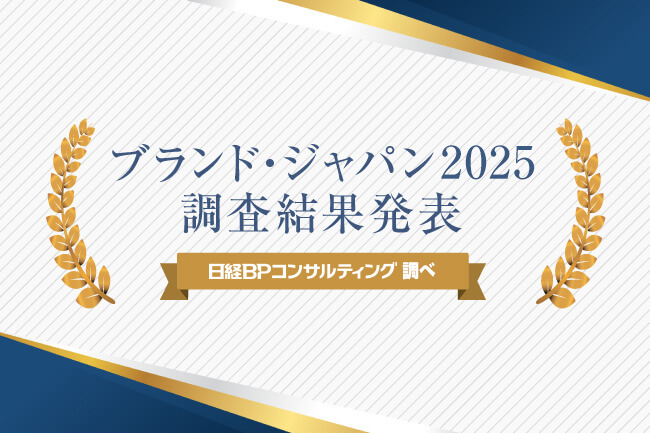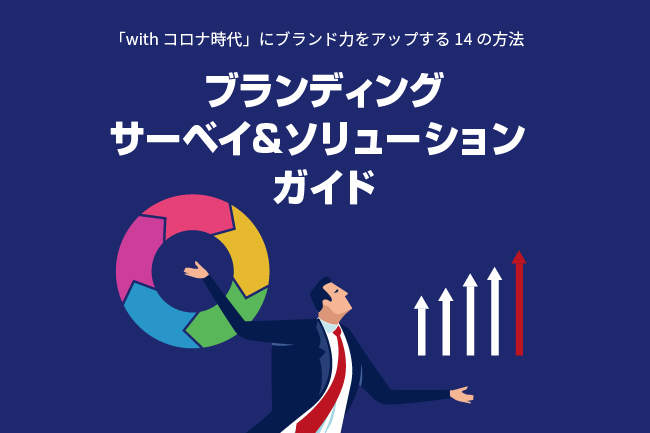企業ネガティブ・イメージ調査2025
企業のネガティブなイメージからみえる、見過ごしがちな「影薄ブランド」の存在
「企業ネガティブ・イメージ調査」とは
株式会社日経BPコンサルティング(東京都港区)は、ブランド価値評価調査プロジェクト「ブランド・ジャパン」を毎年実施しており、今年で25年目を迎えた。本調査は、一般生活者編とビジネス・パーソン編から構成されており、ノミネートブランドに対するポジティブなイメージをそれぞれ尋ねている。よって、調査票上の選択肢となるイメージ項目は、「好きである、気に入っている」「一流である」「品質、技術が優れている」「環境に配慮している」など、肯定的な語句を採用している。
今年は、本プロジェクト25周年の節目ということで、これらの肯定的な語句から否定的な語句に変更したものを選択肢とした、企業イメージをネガティブ・マイナス面でとらえる「企業ネガティブ・イメージ調査」を5年ぶりに実施した。対象ブランドは、ブランド・ジャパンのビジネス・パーソン編にノミネートされている500企業で、ネガティブ・マイナスイメージについて、当てはまるイメージを選択いただくというもの。例えば、「この企業に好感を持てない」「二流、三流である」「品質が低い、技術力が低い」「環境への配慮が足りない」といった具合だ。調査対象者は全国のビジネス・パーソンとした。
「企業ネガティブ・イメージ調査」の意義
一般的にあまり例のないネガティブ・イメージを選択肢としたこの調査。調査の結果から、ポジティブな項目だけでは見えにくい「避けられている理由」「選ばれない理由」「信頼されていない理由」といった企業イメージの弱点や課題を客観的に把握できる。また、改善点を特定しやすくなる。企業のコミュニケーション戦略において、打ち手の優先順位や施策の具体性が高まるだろう。
また、競合他社と比べてどのネガティブ項目で評価が低いのか、どこで負けているのかが明らかになることで、ポジティブ・ネガティブ両面から、差別化のポイントがより立体的に捉えられるようになる。
そもそもネガティブなスコアが総じて高いと、将来的にも継続的なブランドリスクとなり、想定しているほどの広報効果が出ない可能性もある。そして、ネガティブ項目に一定の票が集まっているという事実は、社内への危機感の共有や、改善活動の正当性を裏付ける根拠として活用できるであろう。
過去にもこの「企業ネガティブ・イメージ調査」を実施したことがあったが、「想定していた結果」としては、直近で不祥事を起こした企業のネガティブイメージスコアが高かった。逆に、「意外だった結果」としては、選択肢となる31個のネガティブ・イメージ項目について、「どれも当てはまらない」という回答が全体の5割も占めた。SNSでは生活者の企業への不満を見かけることがあり、企業側も炎上リスクに気を揉んでいる。そのような中で、企業に対してすでに、何かしらのマイナスイメージを生活者がお持ちだろうと思ったのだが、回答者の半数もの人が「聞かれてもそこまでマイナスなイメージは持っていない」と答えた。深いところで嫌いなわけではないのだろう。となると逆にここでのマイナスイメージのスコアは真に迫った確認すべき重要なスコアとなりえるだろう。
ポジティブ×ネガティブの4象限でみえる「影薄」ブランド
さて、企業ネガティブ・イメージ調査を実施したことで、ノミネートブランドのポジティブとネガティブなイメージの両側面をとらえることが可能になったが(散布図1)、そもそもポジティブ、ネガティブのイメージを回答者が持っているかについて確認する。この散布図の横軸は、ブランド・ジャパン2025のビジネス・パーソン編のイメージ25項目のうち、いずれか1つでも選択した回答者の比率、また、縦軸は企業ネガティブ・イメージ調査2025のイメージ31項目のうち、1つも選択しなかった回答者の比率である。
よって、この散布図において、「ポジティブ×ネガティブの4象限」のマトリクスができる。各象限は、それぞれこのように説明できるだろう。
- A群【理想的】
- 高ポジティブ×低ネガティブ(該当158社。500企業のうち31.6%)
- B群【賛否両論】
- 高ポジティブ×高ネガティブ(103社。同20.6%)
- C群【影薄】
- 低ポジティブ×低ネガティブ(113社。同22.6%)
- D群【逆風、脆弱】
- 低ポジティブ×高ネガティブ(126社。25.2%)
A群は、ポジティブなイメージをしっかり醸成しながらも、ネガティブなイメージはあまりないという、イメージ戦略がまずは理想的な方向で進んでいる企業群である。B群は、強みとなるポジティブなイメージがしっかりと醸成できているが、ネガティブなイメージも強くなっているため、イメージや印象に対して賛否が分かれる企業群である。
C群は、ポジティブ、ネガティブのいずれのイメージもない、存在が希薄で影薄になっている。認知とともに、強みとなるイメージを積極的に訴求していくことが求められる企業となる。そして、D群はポジティブよりもネガティブなイメージが強くなっているので、ネガティブなイメージを払拭しつつ、強みとなりそうなポジティブなイメージを高めていくことが求められる企業群である。
さて、一見すると、この4群のうち、D群が一番危機的な状況に置かれているように思われる。確かに明確なネガティブ・イメージを保有することは良い状態とはいえない。「認知はされており、何かしらの良くないイメージをもたれている状態」なので、今後はブランディングやイメージ戦略を推進し、改善を確実に遂行する必要がある。ただ一方で、「影薄」のC群にも着目したい。この群の企業は、現状、人々の頭の中に、良くも悪くもイメージがないに等しいので要注意である。ポジティブどころかネガティブなイメージをほとんど持たれていないということは、そもそも社会・世間からの認知や興味・関心がない、または極めて低いことを意味する。この「無関心」という状態は厄介だ。存在感が希薄なままでは、ブランディングそのものが有効な手立てになりにくく、現在「なんとなく」選ばれている状態に陥っている可能性が高い。こちらもD群と同様に、戦略的なブランディングやイメージ戦略を推進する必要がある。
なお、各群を個々の企業でみると、A群は外資系IT(Apple、Google)と日系老舗メーカー(森永乳業、トヨタ自動車、味の素など)、B群は日系BtoB企業、C群は日系のカタカナ名(英語表記)の企業、D群は以前不祥事を起こした企業などが各群で多い印象だ。理想的な企業像であるA群に該当する企業はわずか3割に過ぎず、7割の企業は、「賛否両論」「影薄」「逆風、脆弱」に該当する。ポジティブ意識を尋ねる調査で仮に高評価だったとしても、うかつには喜べないだろう。
散布図1:「ブランド・ジャパン2025で、ポジティブ・イメージあり」の比率と、「企業ネガティブ・イメージ調査2025で、ネガティブ・イメージなし」の比率(%)
ビジネス・パーソンの自社に対する本音を探り、効果的なブランディング施策の検討を
2025年4月に発行した「企業ネガティブ・イメージ調査」の結果は、500企業をビジネス・パーソンの視点からネガティブな評価を探る珍しいツールだ。このデータを活用すると、自社に対する世間の“本音”がみえてくるかもしれない。多角的なブランディング施策の検討・立案、また継続的なPDCAサイクルの一環として、ぜひ活用いただきたい。
自社のポジションにご関心がある方はこちら
ブランディング、ブランド調査に関するご相談やお問合せはこちらから
ブランド本部長 兼 大学ブランド・デザインセンター長
吉田 健一
慶應義塾大学経済学部卒業後、IT企業を経て、日経BPに入社。日経BPコンサルティングに出向し、2001年より始まった日本最大規模のブランド価値評価調査「ブランド・ジャパン」ではプロジェクト初期から携わり、2004年よりプロジェクト・マネージャーを務める。
企業や大学のブランディングに関わる調査、コンサルティング業務に従事する傍ら、各種メディアへの記事執筆、セミナー講師などを務める。著書に『リアル企業ブランド論』『リアル大学ブランドデザイン論』(日経BPコンサルティング)がある。
※肩書きは記事公開時点のものです。
ブランド本部 ブランドコミュニケーション部 コンサルタント
大平 望実
慶應義塾大学院で心理統計を学び、日経BPコンサルティングに入社。各種ブランド調査を担当し、「企業ネガティブ・イメージ調査」「企業メッセージ調査」のプロジェクト・マネージャー。2023年から「ブランド・ジャパン」の調査にも携わる。
※肩書きは記事公開時点のものです。