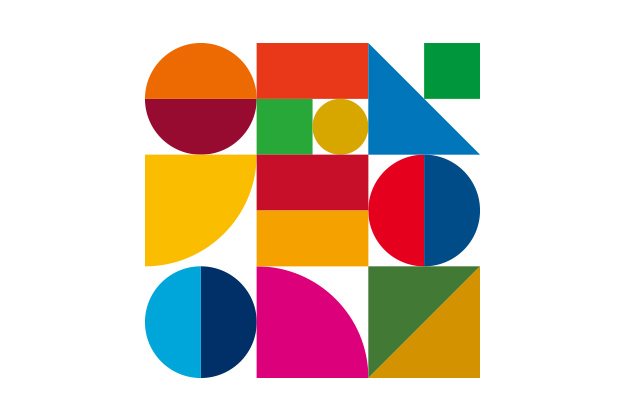「歓びと感動」を問い続けた130年。自社のDNAを研究で掘り起こし、未来の無形資産に変える
空間づくりの現場で培われてきた感覚や経験則を、科学的・学術的な方法で検証する研究活動にはどんな意義があるのか。これを「自社の無形資産を掘り起こし、未来につなげるチャレンジ」と捉える、乃村工藝社サステナビリティ推進室長の古田陽子氏に話を聞いた。 取材・文=酒井 亜希子 写真=吉澤 咲子
『空間の歓びと感動学 あの場所で感じた“なんかいい”とは──』
乃村工藝社「歓びと感動学」プロジェクトチーム 著
「歓びと感動」が形づくる乃村工藝社のDNA
乃村工藝社にとって、「歓びと感動」という言葉はどのような意味を持つのでしょうか。
株式会社乃村工藝社
サステナビリティ推進室長
古田 陽子 氏
乃村工藝社は、万博パビリオンから商業施設、ホテル、ミュージアムまで、人が集う場を130年以上にわたってつくり続けてきました。その根底にあるのが「人々に『歓びと感動』を届ける」というミッションです。「歓びと感動」は長く受け継がれてきたもので、ベテラン社員も含めて、皆がこの言葉を大切にしてきました。
クライアントだけでなく、その先の来場者や利用者も含めて、良い意味でお人好しなくらいに相手がよろこぶことに徹してきた会社のDNAが、この「歓びと感動」という一言に表されていると実感しています。
とはいえ、その「歓びと感動」は長く暗黙知のままだったのでしょうか。
130年続けてこられたということは、目に見えない「乃村らしさ」という土台が必ずあるはずなのに、知的財産のような形ではきちんと整理されておりませんでした。毎年1万件以上の空間をつくり上げているビジネスの背景にある無形資産を、きちんと掘り起こしたいという問題意識が、数年前から社内で高まっていました。
近年、非財務資本の重要性が注目されるなかで、「当社は実は非財務資本の宝庫なのではないか」と気づきました。とりわけ「歓びと感動」は乃村工藝社の根幹にある価値観であり、それに関わってきた人材や培ってきた知見、幅の広いネットワークなどは、他社には真似しにくい競争力の源泉だと考えています。
答えのない研究を100年単位で続ける
そんななかで、なぜ「歓びと感動学」という研究プロジェクトを立ち上げたのでしょう。
私は長く、商業施設のプランニング業務を担当してきました。プランニングとは、市場や想定される利用者を調査・分析し、空間の目的とコンセプトを言語化して企画にまとめること。大規模な複合施設では、定量・定性調査を綿密に行い、その施設が所在する地域社会のサステナビリティも含めた、お客様の投資判断の土台となる計画や事業性のストーリーと戦略をつくるのが仕事です。
一方で、デザイナーや設計者は膨大な経験値のなかで、「この広場の寸法だと人が滞在しやすい」「通路の曲率をこれくらいにすると歩きやすい」といった、暗黙知を豊富に持っています。
しかし、そうした知見は多忙な業務の中で、往々にして各社員のナレッジとして属人化したままで、社全体のナレッジマネジメントはまだ道半ばの状態です。そのため検証も継承も難しい。「歓びと感動学」の取り組みは、その暗黙知を形式知として整理し、会社の資産にしていく試みの一環でもあります。
2021年の社内公募をきっかけに、「感動空間をつくってきた会社として、科学的・学術的に向き合ってみよう」と部門横断で数十名の有志が集まり、「歓びと感動学」のプロジェクトがスタートしました。
そこから3年半の「歓びと感動学」の活動が書籍になった反応はいかがでしょうか。
書籍としてまとめた後に社内共有会を開いたところ、社員から「自分の案件にも使えそう」「こんなプロジェクトで協力してほしい」といった具体的な問い合わせが多く寄せられました。これまで研究チームの活動は見えづらかったのですが、各テーマの担当が内容と活用イメージを丁寧に説明したことで、社員が自分ごととして捉えられるようになったと感じています。
若手からは「研究にも参加したい」という声も出ています。ただし本業と並行する必要があるため、本人の意欲だけでなく上司の理解が重要です。そのため、上司向けのセミナーもあわせて行い、現場での活用と参加体制づくりを進めています。
空間における感動の正体を追い続けるという終わりのないテーマに、企業として今後はどう向き合っていく考えですか。
おそらく一生かかっても研究は完成しないと思います。感動は人の深層心理や文化背景、環境要因が複雑に絡み合う現象なので、「はい、これで定義ができました」とはならないからです。
だからこそ、答えを急ぐよりも「問い続けること」自体が大事だと思います。気づいたら130年が過ぎていた――それが今の乃村工藝社であり、ある意味、お客様と共に壮大な実証実験を積み重ねてきたとも感じています。ですから、これからも小さな知見を積み上げることで見える景色があるはずです。その営みを100年スパンで続ける研究にしていきたいですね。
今後、研究活動がイノベーションにつながる可能性はありますか。
イノベーションの定義にもよりますが、世の中的にはイノベーションを新製品・新サービスの開発と捉える傾向にあるのに対して、私たちが目指しているのは「すでにある豊かなストックを掘り起こすこと」に近い取り組みです。
イノベーションはまったくの新発見ではなく、既存の要素の新しい組み合わせとも言われますが、私たちもまさにその捉え方をしています。
当社は既存事業のシェアが大きいですが、そこに研究で得た知見や新しい視点を少しずつ重ねていくことで、同じ事業領域でもこれまでとは異なる価値を持つサービスへと転化させていくことができる。この積み重ねが、新たなビジネスや提供価値の広がりにつながっていくのだと感じています。
空間そのものではなく、体験価値を売る
空間を生業とする企業のサステナビリティについて、どう捉えていますか。
財務資本は過去から現在までの結果で、非財務資本はストックでありながら、同時に将来への期待や希望を語るものだと言われます。
これまで投資家の方々との対話では、どうしても短期目線の話に終始しがちで、長期のストーリーをうまく語れていませんでした。そんな時、ある100年企業のサステナビリティ部門の方から「空間ビジネスで100年以上続いていること自体がサステナビリティですね」と言われて、はっとしました。
それ以来、今回の「歓びと感動学」を通じて、会社のDNAをストーリーとしてどう語るかを真剣に考えるようになりました。創業者・乃村泰資が芝居の演出で、馬の着ぐるみの目にからくりを仕込んで一筋の涙を流す仕掛けを施したり、昭和初期に夏の国技館のイベントで雪を降らせる演出のために社員総出となりカンナで氷を削って雪を降らせる演出をしたり――。人々を感動させてきた象徴的なエピソードは社内で共有されており、多くの社員が乃村らしさを体現するストーリーとして、自らの仕事に活かしています。「人を感動させるためにそこまでやる会社」であることを、短期利益のグラフだけで終わらせず、きちんと語っていきたいと思っています。
空間づくりが、今後も社会に必要とされ続けるために、何が重要だと考えていますか。
当社の経営理念には「人間尊重」「新しい価値の創造」「目指す企業像」の3つがありますが、そのなかで私は「新しい価値の創造」に特に共感しています。
具体的には「人と人、人ともの、人と情報が交流する新たな機能と可能性を追求し、最適な集客貢献と空間創造を実現する」と掲げています。つまり私たちの仕事は、「床・壁・天井付きの箱」をつくることにとどまらず、「人と何かの関係性」を生み出すことです。物理空間だけでなくデジタルを含む情報空間も含めて、関係が生まれる場はすべて「空間」と捉えられます。
かつてフィリップス社が「電球」ではなく「明るさ」を売ることにビジネスモデルを変更したという有名なエピソードがあります。その例になぞらえるなら、乃村工藝社は「空間」そのものではなく、空間による「歓びと感動」を売っている会社だと言えます。つまり、空間がもたらす体験そのものを価値として提供している、ということです。さらに面白いのは、「歓びと感動」は時間に縛られるものではなく、一瞬から数十年に及ぶ様々な時間軸で起こりうるものです。
そう捉えると空間の可能性は一気に広がります。これからの若い世代には、130年かけて蓄えてきたストックを活かしつつ、さらに新しい要素を加えて「人と人、人ともの、人と情報」の新しいつながり方を更新していってほしい。そこに、乃村工藝社のサステナビリティ、つまり次の130年のフィールドがあると感じています。
サステナビリティ本部コミュニケーション企画部 部長
酒井 亜希子
企業出版、広報誌、オウンドメディア立ち上げなど、コーポレート・コミュニケーション支援に長年従事。現在は統合報告書をはじめとする企業のサステナビリティ領域のコミュニケーション戦略を担当。
※肩書きは記事公開時点のものです。