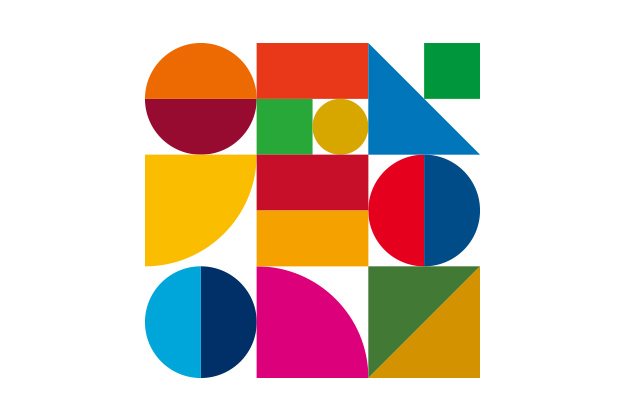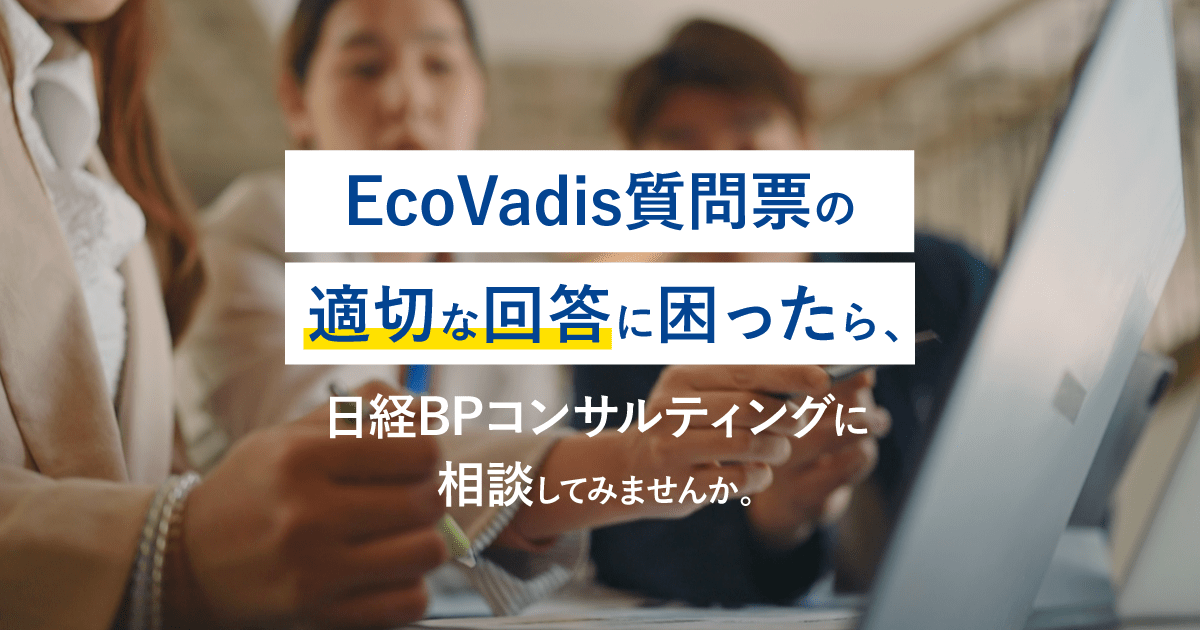世界で拡大するサプライチェーン管理、規制緩和・右傾化の影響は? EcoVadis、パートナー戦略で日本企業の調達管理強化を後押し
EcoVadisはこのほど認定パートナーの条件を見直し、認定トレーナーが最低5名以上所属するなどの基準を打ち出しました。この狙いは何でしょうか?
若月 EcoVadisは評価機関であるため、回答企業に対するコンサルティングは実施しないことにしています。一方、回答するサプライヤー企業が増えていく中で、評点が一定の水準に達していない企業をどのように引き上げていくかという課題がありました。そうした会社へのアドバイスはまさに外部の認定パートナーの力が必要となります。また、バイヤー企業(評価依頼企業)は優先サプライヤーの選定や、サプライヤーのエンゲージメント向上に苦労しており、そこでも認定パートナーの力が必要となります。
スコア(評点)はEcoVadisが判定しますが、その前後でのサプライヤー企業側の組織体制を変えていく役割を認定パートナーに期待しています。今回の変更により、認定パートナーの水準がさらに向上することを期待しており、これがサプライヤー企業の底上げにつながるはずです。
エコバディス・ジャパン株式会社
代表取締役
若月 上 氏
(写真:稲垣純也、以下同)
第2次トランプ政権が始まって以来、反ESGとの言葉も聞かれるようになりました。サプライチェーン管理への影響はありますか?
若月 サプライチェーン管理では企業の調達担当者が窓口となります。従来はQCD(品質・コスト・納期)的な発想で管理してきましたが、そこに気候変動やパンデミックの問題が加わり、紛争・戦争が発生し、さらにトランプ関税の問題も絡んできました。
一部では、企業が米国での取引を控え、欧州にシフトさせるという動きも指摘されています。その動きが一層広がれば、サプライチェーン管理の動きもさらに拡大すると見ています。
一方、欧州でも政治イデオロギーの右傾化が指摘されています。サステナビリティは元来リベラル色が強く、保守的な考えが台頭すれば企業においても財務的な考え方が強くなるかもしれません。それは一時的には逆風になるかもしれません。
ただし、例えば気候変動においても、CO₂を減らさなくてはいけないという意識は多くの人に根付いています。ですから、動きが緩む面はあっても、いずれまたより戻しが起こると見ています。
EU(欧州連合)が打ち出したCSRD(企業サステナビリティ報告指令)やCSDDD(企業サステナビリティ・デュー・デリジェンス指令)も、結果的に対象範囲が狭まり時期も延びました。しかし、こうした規制が撤廃されたわけではありません。これまで急速に義務化を進めたことにより、企業に大きな負担を強いてしまった面もありました。今回、条件が緩んだことにより、今後は企業への負担が是正され、時間をかけながら浸透・拡大していくでしょう。
サプライチェーン管理に着手する日本企業は増加しており、意識も高まっていると感じます。実際のところはどうでしょうか?
若月 2019年にEcoVadisの日本法人を設立して6年半ほど経ちました。当初は、企業は株主のモノであり、企業に言うことをきいてもらうには株主からプレッシャーを掛けるしかないというムードでした。その後に、取引先や従業員も含めたマルチステークホルダーの目線が浸透し始め、株主資本主義的からステークホルダー至上主義へと企業経営における大転換がありました。
EcoVadisにバイヤーとして加盟する企業は世界で約1500社ほどです。そのうち、日本ではまだ50社を超えたくらいです。この50社はいわゆる多国籍企業というイメージを有する企業です。
パリ本社からは常に日本企業の成熟度を問われます。設立当初は正直に言うと、欧州企業と比較するとまだ低かったのですが、最近は向上しています。今ではほとんどの上場企業が何らかの形で調達関係のアンケートを実施しているでしょう。プライム上場の企業では取り組んでいないのはまずいと言えるくらいに成熟してきました。
ここにきて日本で急速に普及している印象があります。その背景は何でしょうか?
若月 当初から、日本にはバイヤーにあたる企業が多く、普及の下地があることは見込んでいました。ESGやサステナビリティに関連した問題は、上場企業本体よりもサプライチェーン上、特に上流で発生します。企業が自分たちの中の体制を整えているだけでは、リスクを抑えきれないという考えが日本でも広まってきたのではないでしょうか。
欧州の機関投資家の間では、上場企業の公開情報を見ているだけでは効果は薄く、裾野を広げて評価するべきとの意識が根強い。この流れは日本の機関投資家も同じです。
バイヤー企業は最終ブランド企業という言い方もできます。バリューチェーンが複雑化・多層化している中で、そのトップに立つのが最終ブランド企業です。バリューチェーンの中で児童労働や強制労働といった問題が発生すれば、NGOなどが動き出し、最終ブランド企業に対して問題を指摘し、責任を問います。この考え方は、欧州の規制に反映されています。日本の大手企業もこれに気づき始めています。
日本のバイヤー企業からは、サプライヤーに対するEcoVadisへの参加促進に苦戦しているとの声も聞かれます。中には海外のサプライヤーの方が積極的に回答する傾向にあるという指摘もあります。日本での普及で課題となっていることは何でしょうか?
若月 欧州では企業はレギュレーションに囲まれており、参加せざるを得ません。ですから、EcoVadisへの回答は欧州の現地法人から着手するケースが多いのです。
日本企業内の課題は、マネジメント層の認識ではないでしょうか。欧州では株主からの圧力も強く、トップダウンでサステナビリティへの取り組みを主導します。対して、日本企業はミドルアップで進めようとすることが多い。調達関連部署やサステナビリティ推進室は積極的ですが、上層部は非財務の事象への対応は「コスト」と捉える傾向があり、財務問題に対して優先順位を低く見がちです。
ところが、サプライチェーン上流でリスクが発生した場合、ネガティブスクリーニングを行うNGOの指摘などがSNSを通して拡散されます。レピュテーションリスクが高まり企業価値損失で株価が下がれば、非財務問題が財務問題に直結します。取締役が襟にSDGsバッチを付けるところまではサステナビリティが普及しましたが、まだ財務問題に直結するというところまで理解が進んでいない人が実は多いのです。
これまでESG経営とは縁が無かった中小企業の中に、突然EcoVadisへの回答を求められ困っているという企業も目立ちます。
若月 中小企業が回答を拒否する理由には、知見が無いということと、対応する人材が不足しているということが多い。対応を促すにはバイヤーがどのようにエンゲージメントするかが重要です。EcoVadisでは回答すると0~100点までのスコアが付きます。45点以上を取れればリスクが無い企業ということになるものの、初回からこの数字を超えられる中小企業は少ないでしょう。
そこで、バイヤー企業から是正措置を促され、「これは大変だ」ということで、総務、人事、法務関連の部署も巻き込み全社で対応することになります。スコアが上がれば、マネジメント層も喜び、さらに上の水準を目指そうということで社内のチームワークが良くなっていきます。
実は、大手企業でも状況は同じです。大手企業はバイヤーでもあり、サプライヤーとして回答する立場にもなります。バイヤー会員でもある企業から自分たち自身のスコアが伸びないという悩みを聞くこともあります。
社内を巻き込んで対応するというのはマネジメントの力です。日本の場合、ミドルアップで上伸してもコストが増えるといって止められてしまうケースが多い。
実際にはリスクを放置し何かが起きてしまってからでは遅いのです。
サプライチェーン管理を提供する組織はいくつかあります。改めてEcoVadisの特徴は何でしょうか?
若月 EcoVadisは、元々、バイヤー企業の優先サプライヤーを深堀してリスクを評価するため、アナリストが時間をかけてスコアリングするというスタイルでサービスを始めました。セルフアセスメント式のアンケートでは、回答に義務もなく、恣意的な結果になりがちなことは、投資家も企業も理解しています。一方、EcoVadisでは回答に対して証憑を添付する必要があり、それに対してアナリストが定量評価を行います。
すると、次第に優先サプライヤーではないサプライヤーも網羅的にカバーする必要性が出てきました。そこで、DUNSナンバー(世界中の企業を識別するための9桁のコード)などの識別コードを使用し、これまで約17万社を評価してきたビッグデータをAIに学習させてリスクを色分けするという評価手法を取り入れました。これまで強かった深堀りでの評価に加えて、網羅的に潜在リスクを洗い出すこともできるようになり、2本建てでサプライチェーン管理を企業に提供しています。
サステナビリティ本部コンサルティング部 次長
戸井田 むつみ
アナリストとしてEcoVadis、FTSE、CDPなどの各種ESG評価機関への対応支援を担当。サステナビリティサイト、統合報告書等でのサステナビリティ開示のアドバイザリーも行う。製造メーカー、不動産、金融機関など幅広い業界へのアドバイスに携わる。
※肩書きは記事公開時点のものです。