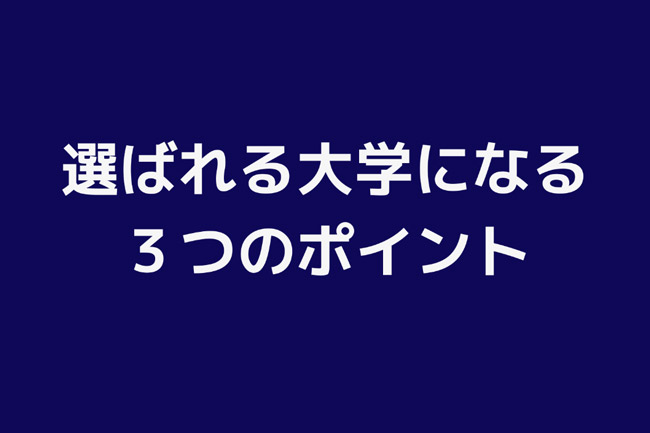まもなく開学30年。教育、研究、地域貢献へ、高知工科大学が挑む「フェーズ3」
高知工科大学
1997年に私立の工科系単科大学として開学してから、まもなく30年を迎えます。
蝶野 開学1年目から教員として在職していますので、本学の歴史をほぼすべて見てきたことになります。初代学長は研究大学を標榜し、早期の大学院開設に尽力されました。通常は開学4年後、つまり1期生が進学するタイミングで修士課程(博士前期課程)を作り、その2年後に博士課程(博士後期課程)を置きますが、本学は開学3年目で修士と博士を同時開設しています。当然、学部からの進学者はいませんから、学外で募ろうと、高知県工業技術センターなどにも訪問しました。
開学4年目は1期生の就職の内定状況が良いことが新聞で取り上げられ、学部の志願者数が増加しましたが、それ以外は入学者確保で苦難の連続でした。新設校は知名度が低く、私立の授業料は高額で、高校を訪問しても良い声が聞かれません。開学初期の頃は、志願者数は毎年漸減の状態でした。
そういった状況下で公立化の議論が始まったのでしょうか。
蝶野 もともと高知県が土地・建物を用意した公設民営の大学なので、2004年の国立大学法人化と地方独立行政法人法改正の際に、公立化の可能性が話題になりました。ただ、実際の検討はその後です。開学時は定員が400名だったのを460名に増やしたものの、2006年に数名の定員割れを起こし、翌年は数十名の定員割れとなりました。それが公立化への転換点で、2008年に既存5学科の定員を各20名減らし、定員100名のマネジメント学部を新設。2009年に日本で初めて、私立から公立大学法人への転換を果たしました。そのあとは学生確保に苦しむことがなくなり、経営基盤も安定しています。2015年には永国寺キャンパスを整備して2キャンパス体制にすると共に、マネジメント学部を改組して経済・マネジメント学群を開設しました。現在は全学の学士課程定員が590名になっています。
公立化で、教育には何か影響がありましたか。
高知工科大学
蝶野 成臣 学長
蝶野 公立になったからということではなく、本学はそもそも人を育てるのではなく「人が育つ大学」という教育モットーを掲げ、開学当初から先進的な教育システムを導入してきました。例えば、1年を4分割するクォータ制を導入したのは、年4回のチェック機能を設けることできめ細かな指導ができるからです。また、学生は一人ひとり将来の目標が違いますから、学生の数だけカリキュラムがあるべきですし、自分の将来は自分で作るという意識が大切ですから、全科目選択制としました。「必修科目がないと、単位を取りやすい科目ばかり選択するのではないか」と心配する声もありますが、本学は学生と教職員の距離が近いことが特徴で、丁寧な履修指導を行うことができるからこそできる仕組みだと考えています。
実は、全科目選択制は教員にとって厳しいものです。本学では、教員の教育活動、研究活動、社会貢献活動を評価して年俸を査定する教員評価制度を採用しています。教育活動は学生による授業評価と履修人数に基づいて評価されます。評判の悪い講義の場合、必修科目だと全学生が必ず履修しますが、選択科目だと履修者は減り年俸も下がります。つまり全科目選択制は、教員は学生にとって有益な講義を目指さざるを得ない仕組みというわけです。
厳しい制度ではありますが、教育の質向上につながりますね。研究についてはいかがですか。
蝶野 開学当初から教員個人の研究を尊重する一方で、学術的な観点あるいは社会の要請などを踏まえて特定のテーマに対して組織的に取り組む学長プロジェクトや学科長プロジェクトも実施してきました。また、1999年には萌芽的な研究にも挑戦できる環境として総合研究所を開設。2015年に特定の研究グループ、特定の研究分野を支援して強化する制度を設けまして、さらに2025年の大幅な改組で、より若手の研究者を支援できる体制を整えています。
一連の改革や変革に対して、教職員から敬遠する声などは上がらなかったでしょうか。
蝶野 もちろん色々な声はありますが、開学以来掲げている「大学のあるべき姿を常に追求し、世界一流の大学をめざす」という志が根底にあり、そのために必要なことは周到に準備して実行するという姿勢を貫いてきました。大学は一般に教授会で様々なことを審議しますが、本学では学長を含む15~20人のメンバーによる教育研究審議会という組織に権限を持たせ、そこで重要な決議を行っています。教授会を議論ではなく報告の場としたことで、高い機動力が保てています。
開学当初からイノベーションの素地を作り、苦難を乗り越えてこられたわけですが、ここへきて新たな取組みが始まっています。まずは2024年4月に新設したデータ&イノベーション学群(D&I学群)についてお聞かせください。
蝶野 日本は世界と比べてデジタル化が周回遅れの状態で、それを担う人材不足が顕著です。特に高知県は課題が多く、6~7年前からデジタル人材を教育する組織が必要との問題意識のもとで議論を進めてきました。近年、多くの大学でデータサイエンスの名を冠した学部・学科が設置され、数理・データサイエンス・AIの教育が広がっていますが、本学ではデジタル化やDXにとどまらず、最先端のICTを自在に駆使することで新たな価値を創造し、社会の変革を引き起こす人材を育成したいと考えました。それが新設のD&I学群です。
D&I学群にはAI・データサイエンス専攻とデジタルイノベーション専攻という2つの専攻があり、前者はデータサイエンスやAIの考え方を身につけ、かつIT情報技術・ネットワーク技術を使って、それらを実現・実装できる人材を育成します。一方、後者のデジタルイノベーション専攻が目指すのは、実業界および公共分野の双方においてイノベーションを起こすことができる人材の育成。課題発見や分析能力、価値創造ができる能力だけでなく、基礎的な経営能力や起業力をもった人材を輩出したいと考えています。
専攻を2つに分けたのはなぜでしょうか。
蝶野 学群は学部に相当する組織で、いろいろな学問分野を横断的に学べることが特徴です。それに対して、専攻は各自の興味や関心、将来の目標に向けて学びを深めるための教育プログラムです。本学にはD&I学群のほかにシステム工学群、理工学群、情報学群、経済・マネジメント学群があり、どの学群でも複数の専攻を設置。学生自身が3年次に上がる際に選ぶことになっています。
D&I学群では全員がデータサイエンスやAIなどの基礎を学び、3年次からデータサイエンスをより深めたいか、イノベーションを志向するかで専攻を決めてもらいます。教育カリキュラムの一番の特徴は、1年次から始まるPBL(Project Based Learning)。学生は6人程度のグループに分かれ、銀行や建設会社、商店街組合等の連携パートナーの支援のもと、調査やデータを活用した解析などを重ねて、地域の課題解決に取り組んでいます。
地域貢献は大学が果たす役割の一つとされています。貴学では2025年4月に地域連携機構を改組し、「地域イノベーション共創機構」を立ち上げられましたね。
大学ブランド・デザインセンター長
吉田 健一
蝶野 地域連携機構は公立化した2009年に設立した組織で、これまでに高知市種崎千松公園地区の津波防護堤防のデザイン、県内18カ所に津波発生検知インフラサウンドセンサ設置、土佐清水市におけるデマンド交通予約システム開発など、様々な分野で成果を挙げてきました。ただ、社会の状況は当時から大きく変化しています。昨今、高知県では人口減少問題が最重要課題になっており、人手不足や人材不足が極めて深刻で、県を挙げてデジタル化やグリーン化、グローバル化に取り組んでいます。
本学としても、これまで以上に専門性を発揮し、地域イノベーションを地域の方々と共に創出していきたいと考え、地域連携機構を4つのユニットに再編し、15のセンター・研究室を持つ地域イノベーション共創機構をスタートさせました。具体的には、①1次産業~6次産業やDX化等の「産業の共創」、②防災・減災や地域交通等の「インフラの共創」、③バイオマス等の「自然との共創」、④STEAM人材やグローバル人材の育成等の「専門人材の共創」を推進していきます。
貴学にとって「地域」は今後の注力分野ということになるでしょうか。
蝶野 きわめて重要なテーマです。本学は先進的な教育システムの私学としてスタートし、企業が採用したい大学ランキングで上位にランクインするなど、優秀な人材を輩出してきました。この期間をフェーズ1とすると、公立になってからはフェーズ2で、教員の増員や研究センターの開設など研究分野に注力。その甲斐あって世界大学ランキングに5年連続でランクインするなど、先端的な研究成果を創出してきました。
私が2年前に学長に就任したときは教育と研究をブラッシュアップするつもりでしたが、高知県と地域の現状を鑑みるに、それだけでは十分ではないだろう、もっと地域のことを考えて地域に貢献できる大学であらねばならないと考えを改めました。これからはフェーズ3として、地域貢献重視の大学運営を行ってまいります。2025年6月には開学の地である香美市と連携協定を締結し、多くの方に「住みたい香美市」「入学したい工科大」と言っていただけるように、シナジー効果の創出を目指して取り組みます。これからも「大学のあるべき姿」を追求し、機動力をもって教育・研究・地域貢献に力を注いでいきたいと考えています。
ブランド本部長 兼 大学ブランド・デザインセンター長
吉田 健一
慶應義塾大学経済学部卒業後、IT企業を経て、日経BPに入社。日経BPコンサルティングに出向し、2001年より始まった日本最大規模のブランド価値評価調査「ブランド・ジャパン」ではプロジェクト初期から携わり、2004年よりプロジェクト・マネージャーを務める。
企業や大学のブランディングに関わる調査、コンサルティング業務に従事する傍ら、各種メディアへの記事執筆、セミナー講師などを務める。著書に『リアル企業ブランド論』『リアル大学ブランドデザイン論』(日経BPコンサルティング)がある。
※肩書きは記事公開時点のものです。