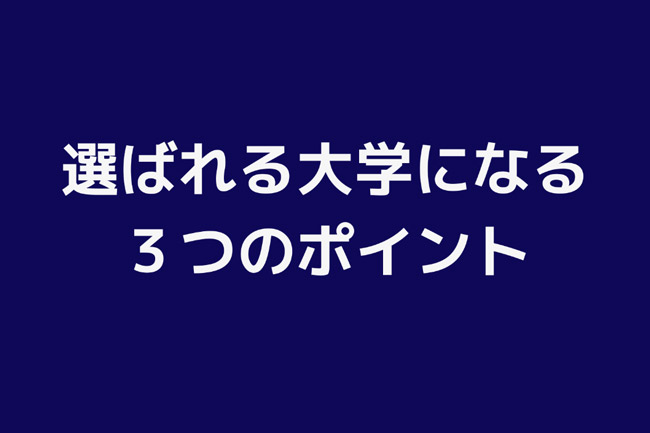描いたのは未来の成長ストーリー
学生だけでなく教職員の視点も変えた動画
岐阜大学
広報ガイドラインの制作から始まった動画
岐阜大学グローカル推進機構の役割と、そもそも留学支援動画を制作しようとした経緯を教えてください。
松井 岐阜大学グローカル推進機構は、地域に根ざした国際化とその成果の地域還元を目的として、前身のグローカル推進本部から参画する兼務教員等の規模を拡大し、2019年4月に設置された組織です。国際協働教育の推進や留学支援、キャンパスの国際化などさまざまな役割を担っています。ただ一口に「地域に根ざした国際化と成果の地域還元」と言っても、多くのステークホルダーが存在し、それぞれに見合った情報発信が必要になります。正しい情報を効率的・効果的に伝達し、岐阜大学の国際性を認知促進しながら個性を発揮していくためには、より良い広報・PR活動が不可欠と当時の調整役(課長相当)と一緒に考えました。そこで2020年にまず日経BPコンサルティングに、ブランディング支援の一環で広報ガイドラインの制作を依頼しました。その中で、現状の広報の棚卸をする際に、「動画による効果的な広報活動」を指摘されたことがきっかけになります。
国立大学法人東海国立大学機構
岐阜大学グローカル推進機構 松井真弓助教
ストーリー動画は、「詰め込み過ぎ」厳禁
岐阜大学は海外留学制度や大学院でのジョイント・ディグリープログラム(国際連携専攻)などの国際展開が充実しています。こうした取り組みを紹介することを目的に動画を制作するにあたって、重視したことや苦労したことはありましたか。
松井 実はこの動画を作る前に、ジョイント・ディグリープログラムを紹介するアニメーション動画を作ったことがありました。しかし、学生の姿をもっとリアルに描いたほうがプログラムの良さが伝わるのではないかということで、今回のようにストーリー性のある動画を制作することにしたのです。
見る人達が自分事としてとらえやすいように、学生をイメージさせる等身大の役者を起用することや、岐阜という場所らしく、山や川など自然豊かな風景とキャンパスが印象に残るような動画になればと考えていました。その上でジョイント・ディグリープログラムについて理解してもらいたいという思いがあったのです。ただ、あまり説明的になりすぎないように意識していました。日経BPコンサルティングからも、絵コンテやシナリオ作りを議論する中で「動画に伝えたいことを詰め込みすぎると、逆に見てもらえない動画になってしまう」とアドバイスしてもらったことは貴重な経験でした。
それでも一部の教職員からは「この要素は必ず入れないと伝わらないのでは」といった要望が随所でありました。そういう意見に対して、詰め込み過ぎることのデメリットを説明して理解してもらう過程が一番苦労したことです。実際にできあがった動画を見ても、過剰な説明は必要ではなく、ストーリーを重視した内容になっているのがとても良かったと感じました。
動画は高校生編と帰国報告会編の2編あり、海外留学に興味のある高校生の岐阜大学での成長を描きながら本学の海外留学の取り組みがわかる内容となっている
https://www.glocal.gifu-u.ac.jp/glocal-lp/
学生や教職員に「そうだったんだ」という気づきを与える
動画公開当初の反響はどうでしたか。2本立ての動画やキャッチコピーに対する評判、学内外に与えた影響についてもお聞かせください。
松井 公開後は学内の教職員から、「キャストは誰か」「コピーはどのように考案したのか」など、さまざまな問い合わせがありました。動画は、高校生編と帰国報告会編の2本制作し、高校生編では高校生が留学に希望を抱いたことから岐阜大学に興味を持つことを表現し、帰国報告会編では留学経験を経て社会に出て行くまでの成長を描いています。この時間軸の異なる2本を制作したことが、メインターゲットとして考えていた学生だけでなく、教職員にも理解を促す効果があったことがわかりました。
そもそもこの動画の企画や構成は、ジョイント・ディグリープログラムがスタートした当初に考案したので、その時点ではプログラムに参加した学生が「将来どのように成長するのか」はまだ実績や具体例を示すことができませんでした。そのタイミングだったからこそ、2段階に分けた成長のストーリーを動画でイメージしてもらうことで、グローカル推進機構のジョイント・ディクリープログラムが目指す成長やキャリアを伝える内容にしたつもりでした。学生には「自分もこのように成長したい」とイメージを持ってもらえる内容に仕上がったと思います。
「そうだったんだ、私。そうだったんだ、岐阜大学。」というキャッチコピーは、今の岐阜大学にもよく当てはまっている表現だと思っています。「そうだったんだ」という言葉には、この大学の良さに気づいたというニュアンスがあります。また、岐阜大学は国際的な取り組みを積極的に推進しているにもかかわらず、その認知度は決して高いとは言えません。この動画をきっかけに国際的な取り組みを知ってもらい「そうだったんだ」と感じてほしいという期待感とも合致していました。加えて、高校生が大学に入って自分の可能性に気づくという意味が込められているところもよいと思いました。
教職員のモチベーションにも好影響
先ほどの教職員にも効果があったという点は具体的にどのようなことだったのでしょう。
松井 この動画は学外に向けて本学の国際的な取り組みを知ってもらうことが第一の目的でしたが、インナーブランディングという想定外の効果がありました。グローカル推進機構の活動を支えているのは、数人の専任教員を除いて、ほとんどが各学部の教員の兼担です。よって多くの教員はこのグローカル推進機構が具体的に何をして、学生にとってどのような学びを提供しているのか理解度がまちまちな状態で活動に加わることも少なくありません。この動画を通じてプログラムの教育やキャリア支援を担う教職員にも、「このような学生を育てるためのプログラムだったのか」という理解も促すことができたのです。動画を見た教員からは「実際の学生たちにも動画のストーリーのように成長してもらいたい」といったコメントもありました。このことが教職員のモチベーションにつながった部分は大いにあるととらえています。
また、教職員の間では、教育プログラム等に対する補助金や助成金などの申請の際には、「学生にどのような成長を提供できるか」といったストーリーを意識して記述することが徐々に浸透するようになったと思います。少なくとも、学生がどのようなステップで成長していくのかをプログラムの設計段階で具体的にイメージすることの重要性が理解できました。
実はこの動画制作の経験から学んだことを生かして、2025年7月には、『ゴジラ-1.0』やカンヌ国際映画祭受賞『怪物』のプロデューサーである山田兼司氏と、脳科学者で作家の茂木健一郎客員教授、マレーシア出身で岐阜大学の国際展開を牽引するリム・リーワ副学長によるシンポジウムを開催しました。ストーリーの持つ力をテーマに、学生自身がストーリーを持つことで他者を惹きつける力が身に付くことを早い時期に知ってもらうことをねらいに企画しました。
岐阜大学シンポジウム・GU-GLOCALシンポジウム2025『日本の魅力を発信! ストーリーの力×グローカル視点=?』の様子
イメージしづらい対象こそ動画で表現
今後、この動画シリーズの続編や新たな広報展開などは、どのようにお考えでしょうか。
松井 岐阜大学には「そうだったのか」と思える取り組みがまだたくさんあります。私はグローカル推進機構のほか、地域連携推進本部地域協学センターの兼務教員でもあるのですが、このセンターが行っている全学共通教育科目を履修する中で段階的に「地域リテラシー」を備え、地域の中でリーダーシップを発揮できる人材を育成する、次世代地域リーダーの育成も入学前の学生さんたちに、もっと知ってほしい取り組みの一つです。
学部学科での専門教育とは異なる学内のプラスアルファの教育・研究プログラムなどにスポットを当てられればと思います。そういった支援プログラムのほうが学内外から明確なイメージが持ちにくい部分があるので、ストーリー性のある動画にする価値が高いのではないでしょうか。
グローカル推進機構の動画が学内の目に留まり、岐阜大学、中部学院大学及び岐阜市立女子短期大学が連携する教育プログラム「地域活性化人材育成事業~SPARC~」の動画も制作
https://gia-gifu.jp/collabo/
広報施策全般へのマインドセットに変化を促す
最後に、動画制作を考えている大学の方々に向けて、メッセージやアドバイスをお願いします。
松井 シナリオの中に教育内容をたくさん盛り込みたくなる気持ちをぐっとこらえて、説明ばかりの動画にしないことだと思います。動画は大学に興味を持ってもらう入口に過ぎません。ターゲットとするステークホルダーに少しでも関心を持ってもらえれば、後は資料請求やホームページ閲覧といった具体的な行動につながるので、動画で全部を説明する必要はないのです。それは動画に限らず、イベント告知のために配布するフライヤーなどでも同じだと思います。しっかりイメージが伝わるビジュアルになっていて、興味さえ持ってもらえれば、詳しいことはWEBページに掲載すればいいはずです。ストーリーを少し意識することで本当に伝えたいことは何か、プログラムの本質について整理する機会にもなると思います。
最終的には広報活動に関わる教職員のマインドセットをそのように変えることが一番重要ではないでしょうか。大学はブランディングのためにさまざまな広報誌策を企画し、コンテンツなどを制作します。その中でも一つひとつのコンテンツで説明しすぎないほうが内容に普遍性があり、長い期間活用できるというメリットもありそうです。
ブランド本部 ブランドクリエイティブ部 兼 大学ブランド・デザインセンター コンサルタント
廣田 亮平
2007年に日経BP企画(現・日経BPコンサルティング)に入社。大学出版グループに配属され、日経BPムック「変革する大学」シリーズ等の編集を担当。以降、大学の広報誌、ウェブサイト、動画、周年プロジェクト等の企画立案から編集ディレクション、制作などを多数手がける。現在は、大学のブランド戦略・広報活動をワンストップで支援する大学ブランド・デザインセンターのコンサルタントとして大学のブランディングにかかわるさまざまなコミュニケーション課題の解決に取り組む。
※肩書きは記事公開時点のものです。