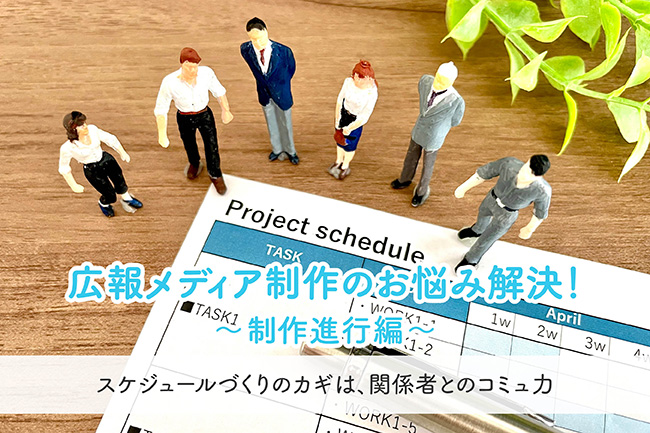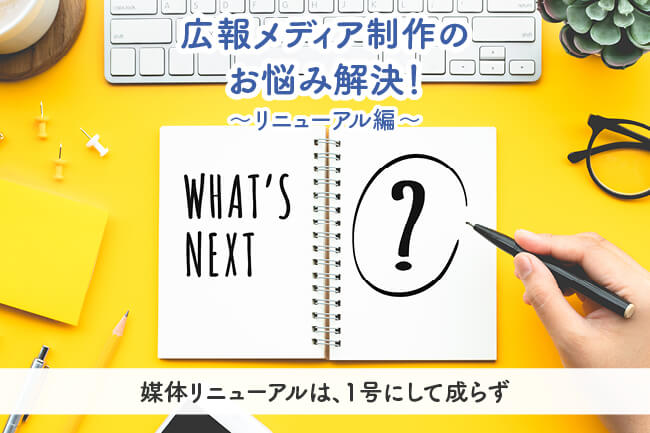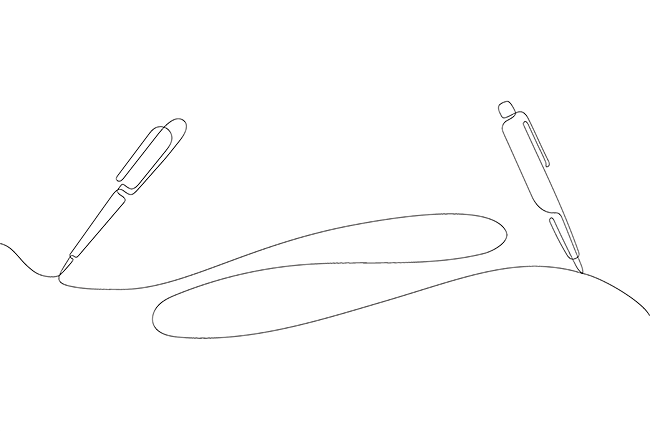思いをつなぐ、つなぐを力に:地方創生の道しるべ
Vol.1 自治体×企業:地域の魅力を発信し、明日を描くために必要な視点とは?
「変わりゆく時代」。変わらぬ思いと、変革期を迎えた情報発信のあり方
スマートフォンなどの普及に伴い、情報収集の方法は様変わりし、人々が重視する情報や、その受け取り方が多様化しています。これらを背景に、私たちを取り巻く環境は、自治体・企業を問わず正確かつ魅力的な情報発信が求められるものへと変化しています。ただ、この時流の変化そのものは、企業にとっても新市場開拓チャンスです。
実際、新型コロナの収束が世界的に進む中、観光やインバウンド需要も再び拡大しています。例えば、世界遺産に登録された厳島神社がある宮島(広島県・廿日市市)では、2024年の年間来島者数が485万人に達し、過去最多になりました。
この過程でオーバーツーリズムによる課題解決のため、IoTテクノロジーを活用としたスマートゴミ箱の設置といった、社会課題解決に向けた自治体×企業のコラボレーションも始まっています。このような状況は、企業にとって自治体と協力しながら新しいビジネスチャンスやブランド力強化、顧客層をつかむまたとない機会です。
また、例えば、移住検討者や観光客が行き先を決める際には、SNSやWebサイトで情報収集をするのが主流となり、魅力的なコンテンツがなければ検討対象になりにくいとされます。まさに情報発信のあり方が、人口減少時代における自治体間競争の明暗を分けます。企業誘致や観光誘客、移住促進の場面でも、他の自治体との差別化が求められています。
そのために、自治体側は定期的に強みを発信し、その地域にしかない独自のブランドや思い、あり方を確立することが不可欠です。一方の企業側は地域にしかない魅力を外部視点から掬い上げ、プロダクトやソリューションとして広く発信していく、という発想や取り組みが必要です。
実際、戦略的な情報発信に成功している自治体では、外部の知見を持つさまざまな企業などと上手にコラボレーションを図りながら、関係人口の増加や地域経済の活性化などの具体的な成果を生んでいます。コンテンツづくりやブランディングは、もはや選択肢ではなく、自治体の未来を左右する必須の取り組みと言えるでしょう。
第2回以降では、約3000人の企業担当者へのアンケート結果を基礎に、自治体と企業がコラボレーションを図るための視点や、自治体×企業の各種の事例などもご紹介しながらそのポイントを探っていきます。連載の初回となる今回は、情報発信の仕方やコンテンツ制作のあり方などを中心に考えていきます。
「リアル×デジタル」の使い分けが戦略のカギ~デジタル社会における情報接触の変化~
昨今は年齢層問わずデジタルでの記事が注目されることが多いですが、保存性が求められる重要な行政情報は紙媒体で記録として残すことができます。手に取りやすい、配布しやすいなどのメリットもあります。一方、タイムリーな情報やビジュアル重視のコンテンツはデジタルでの発信が効果的であると考えられます。両者を組み合わせることで、より幅広い層への情報発信が可能となります。
自治体サイト内のコンテンツだけでなく、定常的に訪問ユーザーが多いSNSやコンテンツプラットフォームの活用にも注目が集まっています。Webプラットフォームの「note」では、トップページのカテゴリに社会>地域・行政があり、自治体・省庁の公式「note pro」アカウント一覧が参照できます。地域別・47都道府県順に並んでおり、ユーザーが探している自治体のコンテンツをすぐに見つけることができ、noteの機能でフォローも可能です。一度フォローしたユーザーには、コンテンツが更新される度に通知が届き、メールマガジンのような役割をもたらします。
選ばれる自治体:地域に根付く思いが人々の共感を呼ぶ~効果的なコンテンツづくり:ターゲットに注目される企画立案~
効果的な情報発信をするためには、企画力が成功のカギを握ります。こだわった写真や動画を用意しても、企画や訴求すべきメッセージ性が弱ければ閲覧者の心には響きにくいでしょう。発信力の高い優れた企画は、次の3つが重要な要素となっています。
1つ目は、明確なターゲット設定。誰に何を伝えたいのか、どのような情報を発信したいのか、詳細に情報を閲覧する人々あり方や行動特性(ペルソナ)を設定することでメッセージの方向性が定まります。例えば、Uターン/Iターンとして就職活動を控えた大学生というペルソナを設定し、地元企業やその自治体で暮らすことの魅力を発信するなど、コンテンツのカテゴリを設けることから始めます。
2つ目は、自治体の独自性の発掘です。例えば、宮崎県日南市では、観光や工芸品、ゆるキャラなどを用いて、“コラボしやすい市”としてのブランディングが成功し、交流人口の増加につながっています。他の自治体との差別化を図るため、自治体ならではの魅力を掘り下げることが重要です。現場だけでなく第三者からの意見にも耳を傾けることで精度が高まります。
3つ目は、定期的に訪問したくなるコンテンツ設計です。更新頻度・カテゴリ分けなど、再訪ユーザーが必要な情報を見つけやすいような工夫が求められます。観光の情報を探している潜在顧客、移住を検討しているユーザーが状況に応じて必要な情報を掴むことで、再訪率が向上します。例えば、環境モデル都市にも認定されている北海道下川町では、自治体公式サイトをはじめ、公式LINEやYoutube、noteでの定期的な記事更新を行っており、町民の有志で起業支援や移住支援に取り組むなど、町おこしに力を入れている好例として知られています。自治体間のコンテンツが充実化している今こそ、企画力の向上は避けて通れない課題と言えるでしょう。
*
地域の魅力を発信するためには、魅力の源泉を調べ、理解し、独自性に気づき、発信する──。こうした各ステップと、効果的な発信に向けたプロフェッショナルな編集力が欠かせません。日経BPコンサルティングは、日経BPグループで培った取材・編集のノウハウを活かし、自治体の情報発信を強力にサポートしています。
また、企業向けコンテンツ制作の実績を生かし、地域の産業振興や企業誘致にも効果的なアプローチに向けた支援も可能です。「選ばれる自治体」になるために、コンテンツ制作のプロフェッショナルが伴走いたします。
日経BPコンサルティング
「地方創生プロジェクトチーム」について
社内インキュベーションプログラムからスピンアウトした、タスクフォース。地方創生支援に熱い思いを持つメンバーが主軸となり、さまざまな情報を継続的に発信していきます。
マーケティング本部 ビジネスアーキテクト部
後藤 葵
埼玉県出身。デジタル関連の“万事屋”。大学院では教育学を専攻。リアル⇔デジタルのメディア効果について日々研究し、各メディアがもたらす記憶保持効果について修士論文を執筆。前職では外資系スタートアップ企業で英語学習ロボット/アプリケーションの開発・マーケティングに携わり、自治体間の教育格差をなくすべく、47都道府県の国公立・私立小学校~大学へ教材として導入した。2024年2月、日経BPコンサルティング入社。福島イノベーションコースト機構の情報発信プロジェクトでは、特設サイトの改修や広告発信に参画。
※肩書きは記事公開時点のものです。
コンテンツ本部ソリューション1部
AI企業コミュニケーション タスクフォース
平野 優介
記者・編集者・防災士。日経BPコンサルティング内のAI企業コミュニケーション タスクフォース所属。中央省庁関連書籍の担当を経て、2011年3月より地方行政の総合誌の記者・編集者、税務分野の月刊誌副編集長に就任。2017年9月、日経BPコンサルティングに入社。NTTデータの30周年事業、NTT東日本の東京2020大会記録事業など、大手企業の周年・イベント記録事業にプロデューサーとして多数参画。また、NTT西日本の「Biz Clip」やBIPROGYの「BIPROGY TERASU」などのビジネスメディアで取材・編集を担当。
※肩書きは記事公開時点のものです。