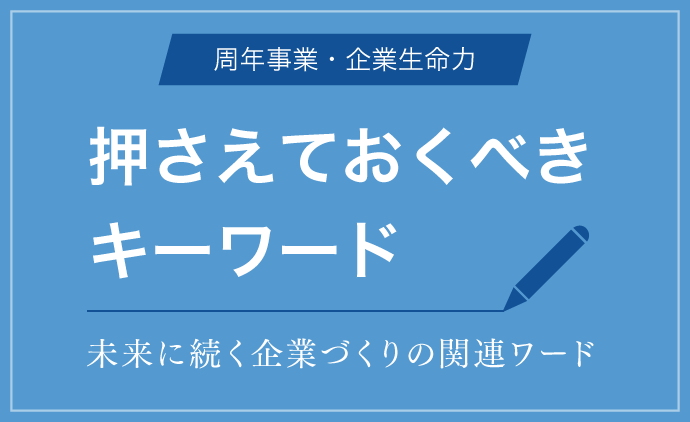サバイバル分析イベントレポート〈日経BP総研フォーラム2017-2018〉
経営課題・社会課題解決のための5つのソリューション
- 文=青木唯/構成=松崎祥悟
- 2017年11月20日
- Tweet


不確実性が増す時代、企業や自治体にとっては、先を見据えた戦略立案・実行プラン策定が大きな課題とされている。そのようななか開催されたのが「日経BP総研フォーラム 2017-2018」だ。
2017年10月31日、ホテル雅叙園東京には約500人の企業経営者や事業責任者が集まった。日経BP総研は、これまで数百件のソリューションを企業や自治体に提供してきたが、そうした事例の中で特に課題視されている旬なテーマが取り上げられた。
冒頭では日経BP総研・酒井綱一郎事業統括が登壇。AIやRPA、ロボット、ESGなど、市場を取り巻く最新キーワードを挙げるとともに、メディア企業出身の日経BP総研の特長を解説。こうして、「経営課題・社会課題 解決のための5つのソリューション」と題するフォーラムが幕を明けた。
経営改革
PART1 長期的な経営課題に先手を打つには?
ESG・SDGsで飛躍する経営改革ソリューション

今、なぜ長期的な視点での経営が必要なのか? まず、日経エコロジー・田中太郎編集長が、昨今の企業を取り巻く状況分析を行った。大きな潮流として、環境規制強化の進行、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)のインデックス運用も影響したESG投資の拡大、企業の情報公開への圧力の高まりを指摘。総括として、直接的な罰則があるハードローの流れから、情報公開によって企業の行動を民間が強制するソフトローの流れが当面は続くとし、NGOの存在感が今後増してくると語った。

これからの企業に求められるのは、時流を先取りして規制に対応していくこと、自社の姿勢を明確に示す情報開示をすること、将来に向けた自社のサステナビリティー(持続可能性)のビジョンを提示することの3つだという。さらに、環境経営で名高いキヤノン、KAITEKI経営という独自の手法で取り組んでいる三菱ケミカルホールディングスの2社によるプレゼンテーションを実施。先進企業の最新事例を紹介した。
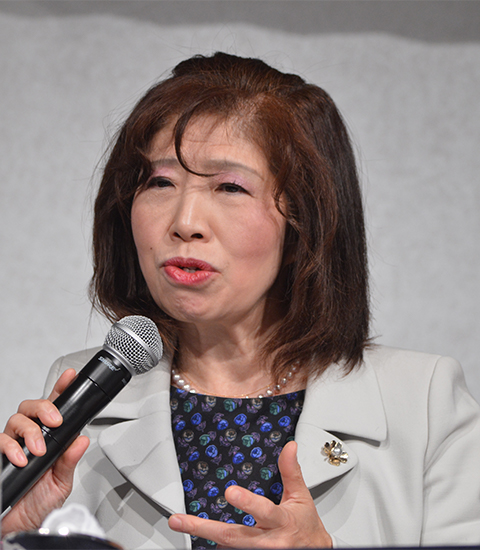
終盤は、田中編集長と両社によるパネルディスカッションに。注目のSDGsについては、企業の取り組みを17の目標にマッピングする段階は完了しつつあり、今後いかにビジネスに展開していくのかなど、本質的な議論が展開された。
PART2 中小企業のための経営強靭化プログラム
中小企業の悩みに対して多面的に対応

「昨今の中小企業の悩みは、圧倒的に求人難」
強い言葉で講演を開始したのが、日経BP総研中小企業経営研究所・伊藤暢人所長だ。2017年8月の有効求人倍率は1.52倍と、バブル期の1.46倍を大幅に上回った。若者の大手志向が強まる一方で、3年で新入社員の3割が退社する時代。中小企業が人手不足問題にいかに取り組むべきかを指南した。
具体的な対策として、(1)採用力を引き上げる、(2)離職率を引き下げる、(3)自社の強み・弱みを知る、(4)体質改善と対策資金を創出する、(5)経営者自身の経営力をアップする、この5つを挙げて解説した。また、「2019年ショック(※)」も見据え、体力のあるうちに2020年以降の対策を練る必要性があることも強調した。
※ 東京オリピンピック・パラリンピック開催によるボランティア参加予定者は約9万人と推計。それにより引き起こされると考える人材難のこと
働き方改革
働き方と事業拡大をどう両立する?
「働き方改革」成功のセオリーをご紹介
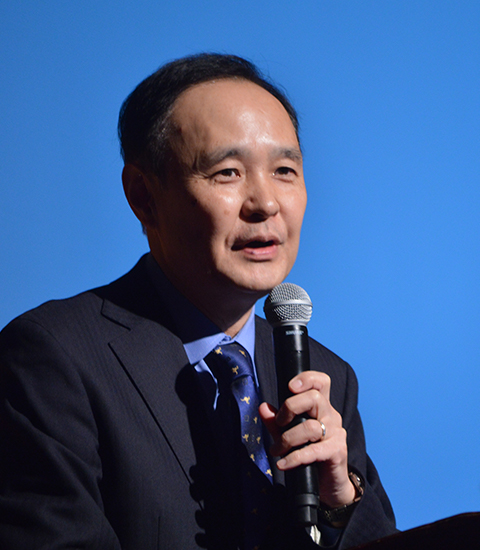
今、多くの企業が注力している「働き方改革」は、労働生産性を改善する最良の手段といわれる。当フォーラムでは、日本のリテンションマネジメント研究の第一人者である青山学院大学 経営学部教授 山本寛氏が登壇した。
「従来の『働きやすさ』の改善だけでは労働生産性の向上は困難。『働きがい』を加えた2軸で考える必要性がある」
こう語る山本氏の講演は、働き方改革の基礎的な知識から最新情報まで、初心者にも分かりやすく展開していった。では、「働きがい」をどう捉えるのか? 複数の側面から考察するなかで、「働きがい」と従業員のエンゲージメントの深い相関性に着目。国内外の調査データをもとに、エンゲージメントを高めることが生産性向上に好影響を与えると結論付けた。

「働き方改革」を支える「働きがい」であるものの、日本は諸外国に比べて従業員のエンゲージメントは非常に低いと指摘。「内容プラトー(仕事における停滞)」という概念を用い、日本の組織や上司は社員を飽きさせない工夫を次々と施す必要があると説いた。また、課題としてサービス業における生産性向上を挙げ、長時間労働の是正を呼びかけた。
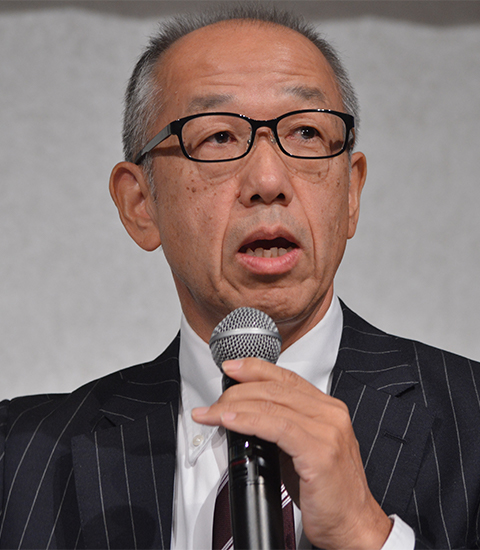
後半のパネルディスカッションでは、日経BP総研マーケティング戦略研究所・麓幸子所長がモデレーターとなり、山本氏と日経BP総研イノベーションICT研究所・桔梗原富夫所長が議論を展開。先進事例の共通項を考えることで「働き方改革」成功のセオリーとして、キーワードに「ICT機器の導入」「ワークフロー面への浸透」を挙げた。
12
- 2017年11月20日
- Tweet

あわせて読みたい
連載「イベントレポート」
- (1)経営課題・社会課題解決のための5つのソリューション
- (2)デジタル時代の経営とブランド戦略
- (3)効果的なデータ活用・分析で、より良い会社をつくる
- (4)共感を生む“らしさ”を意識したコミュニケーション