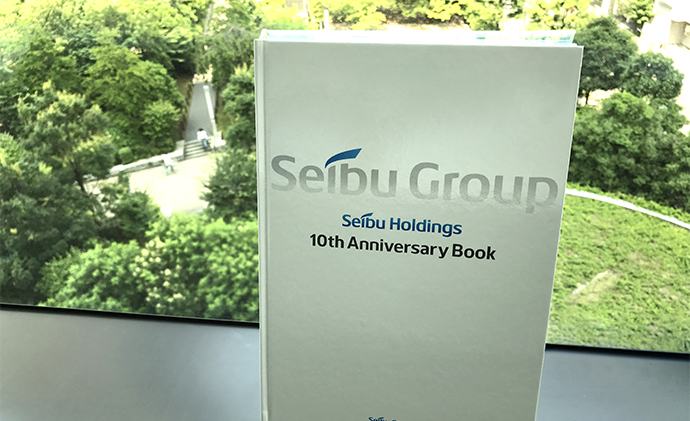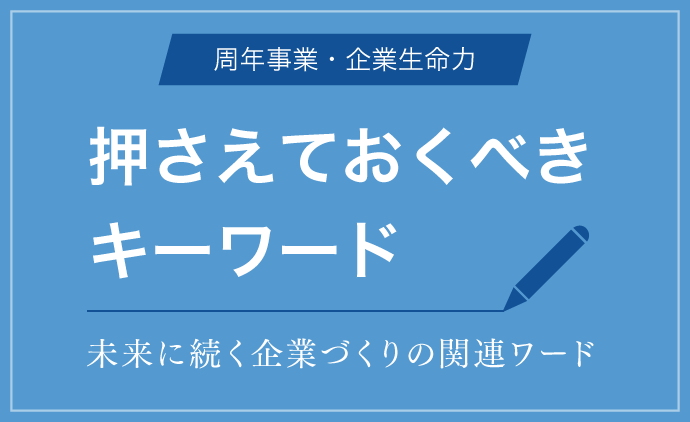サバイバル分析続く企業の“ブランディング”(2)
「リピート」や「口コミ」につなげる真のブランドとは
- 文=吉田健一/構成=松崎祥悟
- 2017年08月21日
- Tweet


続く企業が実践する“ブランディング”について紹介するこの連載。
第1回では、企業のブランド担当者が抱くブランドへの誤解や、社内で進まないブランドに対する議論のために、企業がブランドづくりを遠回りしてしまう現状についてお話ししました。
第2回は、ブランドとはそもそも何なのかについて整理します。
「ブランド」と「コモディティー」
「brand」という英単語を辞書で引くと、「家畜などに押す焼き印」とあります。かつて北欧では自らが所有する牛や馬などの家畜に対し、他人のそれと区別するための「印」として家畜に焼き印を施しました。英語では「burn(焼く)」という単語がありますが、これが「brand」の起源です。つまり、「他とは違うもの」ということを示す行為、差別性の保持が、ブランドのもつ本質的な意味だといえるわけです。
さて、今日の企業経営やマーケティングの世界において非常に重要なキーワードになった「ブランド」は、本来の差別性、識別性だけではなく、それ以上の意味を包含するようになりました。すなわち、「競合他社が出しているプロダクトやサービスと、自分たちの提供するものはここが違うのだ」という「独自性」に加え、他社が提供できないものを提供することで、お客様に喜んでもらい、“いいね!”と「評価」してもらうことが必要になっています。
それは、一般的に「コモディティー」、つまりどのメーカーでも品質に大差がなく、同質化していると言われるような商品よりも、ちょっと格が高いものです。差別化がなされ、お客様を喜ばせることのできるもの、そういったものを今日では真のブランドと呼ぶわけです。そしてこうした高い評価を受けているブランドを提供する企業が、今後この連載で紹介していく「企業ブランド力」が高い企業です。
ブランドとコモディティーの差分の一つとも言える格が高い、つまり「ロイヤルティーが高い」状態とは、例えば、「あの企業が提供している商品なら、間違いはなさそうだ」とか、「あの会社の新商品が出たから、買ってみよう」という具合に、消費者がその企業をひいきにしてくれる率が高まるため、自然と客単価が高まります。これは、商品やサービスを繰り返し使う「リピート」につながり、さらには、他人にアピールしたり、推薦したりといった「口コミ」につながる状況をつくり出します。
つまり、ある商品を「コモディティー」と呼ぶか「ブランド」と呼ぶかは、作っている側ではなく、使っている人が決めるということです。
製造側や、生産者が「これはブランドです」と声高に叫んだところで、それはまったく意味がありません。消費者がその商品を「他の会社が出している商品とはここが違っていてよい」とか、「この商品には、製造元の企業らしさが十分に伝わってくる」といったことを正しく認識してもらえるものだけが「ブランド」と呼べるからです。
「競争の優位性」と「時間の効率性」を生み出すブランド
ただし、消費者がどう思っているかは聞いてみないと分かりません。作り手が「おそらくこういうことだろう」と独りよがりに考えることは極めて危険です。いずれにせよ、現在、この「差別化要因の形成」や「ロイヤルティーの醸成」をどのように図ればよいのかが、ブランドづくりにおける一番の課題になっています。「あの企業(商品)なら間違いない」とどれだけ思ってもらえるかがポイント、というわけです。
自分らしさを伝え、ファンを固定できれば、他社の商品より自社の商品を選んでくれる確率が高まりますから、その分「競争優位性」が働きます。
また社内では、「時間の効率性」を生み出すことができます。そもそも企業ブランドをつくるということは、あらかじめ決めておいた自社のアピールポイントを消費者に理解してもらうことですが、そのためには、まず社内の意識が統一されている必要があります。
まさしく、目指すべきゴールに向けて、全社で一丸となって突き進んでいくイメージですが、「自社にとって企業ブランドとは何か」が明確になっていれば、何か新しい施策を打ちだすときに「それは自社らしくない」あるいは「自社らしい」という判断が瞬時にできるので、会議の時間が短くなり、人的エネルギーを他に振り分けられる。これがすなわち時間の無駄が省けるということです。
ブランドが注目を浴びた陰にITバブルの崩壊
このような企業ブランド育成のメリットを勘案して、日本でもブランドについて考えられるようになりました。その本格的なスタートは、2001年頃、ちょうどITバブル崩壊の時期に遡ります。
米国では1990年代後半から、ドットコム企業と呼ばれるベンチャー系ネット企業が台頭し、株価が急騰しましたが、ほどなくして急落。その影響が日本にも飛び火し、それまで長引いていた不景気と相まって、日本企業も少なからずダメージを受けました。
そのような状況下で、企業も広告・宣伝などコミュニケーション関連のコスト削減が行われ、施策の見直しが図られることになりました。世の中は不況だが、自社の商品は購入してもらわなければならない。そのためにはどうすれば良いか――。この見直しの延長線上で、企業の無形資産である「ブランド」をいかに強くするかについての議論が真剣になされるようになったわけです。
新規開発ではなく、既存の資産に向き合い、それを上手に活用する。また、体系だてたコミュニケーションを図ることなどが話し合われ、製品のラインアップやコミュニケーションのあり方が効率化されていきました。それから早15年あまり。日本企業でも、ブランド視点で考えることがかなり定着してきたように感じます。
しかし、時として「ブランドづくりは、結果が出にくいのでもうやめた」「我々の会社にブランドは必要ない」などという声を耳にすることがあります。
それは、とりもなおさず「ウチの会社は学生や取引先、顧客からどんな(悪い)イメージをもたれても構わない」「ウチは今だけ儲かっていれば、それでよいのだ」と言っているのと同じことです。10年先、20年先の状況を見据えて、企業の魅力を向上させるために様々な手段を講じ、様々な人を巻き込みファンづくりに奔走するという、一連のブランドづくりのプロセスを一切無視すると言っているのです。
このような話が、いまだにまかり通ってしまう背景にはブランドづくりを取り巻く、様々な困難や失敗があります。次回はこのことについて詳しく見ていくことにします。
- 2017年08月21日
- Tweet

あわせて読みたい
連載「続く企業の“ブランディング”」
- (1)大事だと分かっていても、育たないブランド
- (2)「リピート」や「口コミ」につなげる真のブランドとは
- (3)ブランドを取り巻く誤解
- (4)ブランド担当者の心得5カ条
- (5)捉えどころのないブランドを可視化する「ブランド・ジャパン」