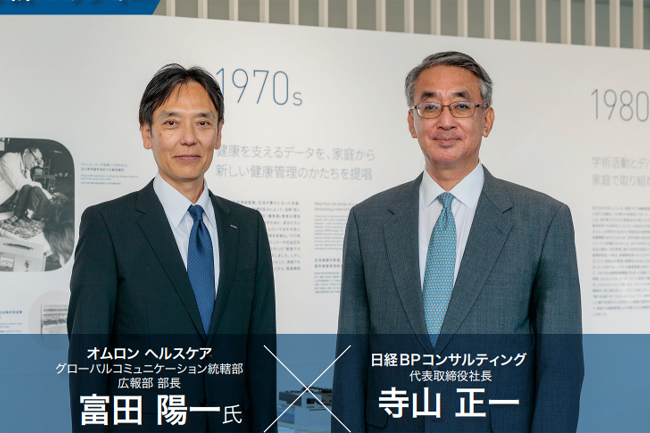【三井ホーム】会員メディアを協働で磨き上げる編集クオリティ
医師向けの情報発信、三井ホーム担当者が実践する品質管理の勘所
三井ホームは注文住宅をはじめ、賃貸・土地活用、施設建築、リフォームなど幅広い事業を手掛け、医院建築事業においても40年以上の歴史と、6000件超(※)の医院・介護施設の建築実績があります。同社Webサイトの「医院建築」カテゴリーには、三井ホームで建築したクリニックの実例紹介や物件情報などとともに、医師限定の会員向けオウンドメディア「WITH DOCTORS」が掲載されています。このWITH DOCTORSは、診療圏調査やセミナーレポートのほか、医業経営に役立つオンとオフの情報に関するテーマ別の書き下ろしコンテンツ「DOCTOR’S宝箱」が収録されています。日経BPコンサルティングは、DOCTOR’S宝箱の企画と記事制作を、2017年8月の連載スタート時からお手伝いしています。
※三井ホームグループによる医院・介護・施設建築実績(三井ホーム調べ 2024年3月現在)
三井ホームの医院建築ページに配置されている会員向けの「WITH DOCTORS」と、オリジナルコンテンツが120以上収められている「DOCTOR’S宝箱」
医師の開業・経営を、DOCTOR’S宝箱を通じて支援
DOCTOR’S宝箱は、医師のオンとオフに役立つオリジナルコンテンツを毎月掲載し、2025年10月時点で120本を超える記事が会員限定で公開されています。「知っておきたい開業のポイント」や、「ポリファーマシー(※)解消へクリニックができること」といったクリニックの開業や運営に直結するテーマはもちろん、「何ができる?どう使う?生成AI活用法」「誹謗中傷や風評被害からクリニックを守るために」といった社会で起きている変化について、クリニック運営に引きつけて対応方法を解説した記事を数多く掲載しています。さらに、「忙しい医師にこそ知ってほしい!疲れを取る休み方のコツ」や「ドクターの副業事情」など、医師のライフスタイルに関わる内容も充実しています。
※多くの種類の薬を服用することで副作用などの有害事象が起きること
三井ホームにおいて、2024年からDOCTOR’S宝箱を担当しているのが、施設・賃貸事業本部 事業推進室 施設営業推進グループ グループ長の野呂瀬應行氏です。「DOCTOR’S宝箱では、開業を検討している医師やクリニックを経営する先生へのご支援やコミュニケーションを目的に、医業経営や自身の生活に役立つ情報をお届けしています。今でこそメールやSNS、デジタル媒体でお客さまとコミュニケーションを取るのは一般的になりましたが、DOCTOR’S宝箱を始めた当時は、当社にとっても新しい取り組みでした」
野呂瀬氏はコンサルティング営業職を経て、DOCTOR’S宝箱を担当しています。媒体を使ってお客さまに提案をしてきた現場経験を生かし、担当就任早々に、医師の会員向けに発信しているメールマガジンの改善に取り組みました。「メルマガはそれまで、シンプルさ優先で展開していましたが、画像を用い、読んでもらうための工夫をしています」
三井ホーム株式会社
施設・賃貸事業本部 事業推進室 施設営業推進グループ グループ長
野呂瀬 應行 氏
年間企画で全体をふかん。制作では文章の品格を重視
DOCTOR’S宝箱は、あらかじめ計画した1年間分の企画テーマに沿って、毎月取材をして執筆・制作しています。企画テーマ案は日経BPコンサルティングが提案。現在は月に1本のペースで新しい記事を公開しています。12回分の方向性をまとめてすり合わせておくと、テーマのバランスが取れるだけでなく、制作・確認期間の確保につながり、不測の事態にも対応しやすくなります。
記事制作の上で難しい点や気をつけている点を伺うと、「記事の企画・制作は日経BPコンサルティングの皆さんがご担当くださっているので、当社は記事の品質管理にリソースを集中できています。原稿を確認する際は、専門用語の使い方やバランスに気をつけるほか、特に心がけているのは文章の品格を守ることです。かたすぎず、砕けすぎず、落ち着いた印象を持っていただけるように。忙しい先生方がさらっと読めるように、記事の分量も長すぎず、スマホでの読みやすさも意識しています」と野呂瀬氏。建築物だけでなく、情報も、三井ホームがお客さまに届ける商品の一つ。野呂瀬氏は、それが「三井ホームが医師向けに発信するにふさわしいトーン&マナーになっているかどうか」「医師の方々が読む際に負担を感じないか」を、医師などのお客さまと接してきた経験をもとに常にチェックしています。
記事制作の手応えと今後の課題
今後の課題は、登録者数を伸ばすと同時に、メルマガ開封率の向上です。現在のメルマガは約2割の開封率があるものの、メルマガで紹介している記事のクリック率は満足できる水準には届いていないとの認識です。「三井ホームは2024年に50周年を迎えました。医院建築としても医師の自宅兼医院を1983年に竣工して以来、40年以上の歴史があります。医院建築は成熟した市場で爆発的な躍進は考えにくい状況ですが、新規会員数とクリック率の増加を目指し、施策を進めていきたいです」
取材協力:三井ホーム株式会社
施設・賃貸事業本部 事業推進室 施設営業推進グループ グループ長
野呂瀬 應行 氏
コンテンツ本部ソリューション2部 部長
渡邉 亜紀子
エンタメ&カルチャー誌の編集者を経て、オウンドメディア編集歴20年強。現在は医療・健康分野を中心に、より良い企業コミュニケーションのデザインづくりに「さってばさあ」の姿勢で取り組む(「さってばさあ」は出身地の方言で「話を聞いたらすぐ動く」の意味)。