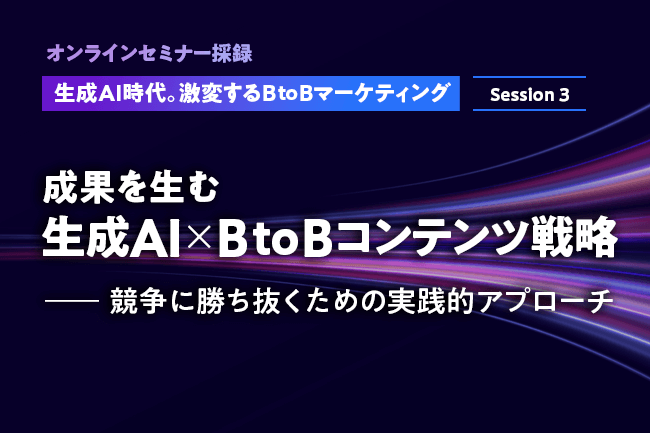【AIツールレビュー】企業コミュニケーションにおけるAI活用の可能性(第3回)
営業用AI「ailead」は広報・IR業務で使えるか? 検証で見えた「使える場面」と「3つの壁」
調査=日経BPコンサルティング 文=菅原 研
広報・IR部門が直面する業務負荷
企業の広報・IR部門は、事業活動や理念の理解、各部門からの情報発信、メディア対応など多岐にわたる業務を担っています。SNSの普及により、発信先は顧客や株主だけでなく社会全体へと広がり、発信内容の精度と多様性が求められるようになりました。採用活動にも影響するため、慎重な情報発信が不可欠です。IR部門では、業績情報に加え、ガバナンスやサステナビリティなどの開示が求められ、決算期には業務量が急増します。こうした状況下で、生成AIが業務効率化やメッセージの質向上に貢献できるかを検証することが、本取り組みの出発点となりました。
営業支援AI「ailead」を広報・IR業務に適用
今回検証に使用した「ailead」は、2017年創業のailead株式会社が開発した営業支援ツールです。同社はAIオートメーション技術を核としたプロダクトとサービスを提供しています。
「ailead」は本来、顧客とのオンライン商談や通話を可視化・解析するツールです。文字起こし、トピック要約、エグゼクティブサマリーの抽出、フィードバック機能などを備えています。
特にフィードバック機能は、事前に設定した「カスタムプロンプト」と実際の会話内容を比較し、改善点を提示することで、質的向上を図るものです。これらの機能を広報・IR業務に応用することで、情報発信の精度向上や業務負荷軽減、経営層のメディアトレーニング支援につながる可能性があると考え、実証実験を行いました。
「ailead」は、ailead社が開発した営業支援ツール。オンライン商談や通話を可視化・解析し、「フィードバック機能」で改善点を提示する。今回、この機能を広報・IR業務に応用することで、情報発信の精度向上や業務負荷軽減、経営層のメディアトレーニング支援につながると考え、実証実験を行った
期待される3つの効果
「ailead」を使うことで、以下のような効果が期待できると考えました。
- 自社が伝えたいメッセージと発表内容・原稿との差異を事前に確認し、調整できる
- 企業理念やパーパス、サステナビリティ戦略との整合性を事前に確認し、メッセージを調整できる
- 会話から要点を抽出することで、プロットや原稿作成の作業量を削減できるほか、多忙な経営層や各部門責任者との調整・打ち合わせを減らし、広報・IR担当者の業務負荷を軽減できる
実際の検証
検証を進めていた7月中旬、日経BPコンサルティングでは2025年版のサステナビリティレポートの作成を進めていました。本レポート内の重要コンテンツであるトップメッセージの取材が8月中旬に設定されていたため、この取材で「ailead」を利用し、主に「文字起こし」「トピック要約」「フィードバック」の精度や、実際のサステナビリティレポートの記事制作への貢献度を検証することにしました。
検証環境の留意点
今回の検証環境には、一般的な企業と異なる特性があります。当社の代表取締役社長は日経BP発行の雑誌「日経ビジネス」の元編集長であり、文章でメッセージを伝えることに対して強いこだわりを持っています。また、コンテンツ制作は事業の中核の1つであり、取材や記事制作を行うスタッフも言葉の選び方や表現に対する感度が高い環境です。このため、後述する「生成AIによる文章の平準化(個性や熱量が失われること)」が課題として浮き彫りになった面があり、一般企業で導入する場合とは評価が異なる可能性があることをあらかじめお断りしておきます。
【検証1】準備段階:検証準備と関係者との意識合わせ
検証は準備フェーズ、取材フェーズ、検証フェーズ、制作フェーズに分けて実施しました。準備フェーズで、特に重要だと感じた点は、生成AIが行う作業と人間が行う作業の切り分けを、入念に関係者へ説明する必要性でした。生成AIに対する期待値は人によって大きく異なるため、「何ができて、何ができないのか」「どこまでをAIが担当し、どこから人間が担当するのか」を関係者全員で共有することが重要です。特にメッセージの発信元が経営層であればより丁寧な事前説明が求められます。
関係者の認識共有のために作成した資料。AIと人間の役割分担を明確化し、生成AIへの理解度が異なる関係者とも共通認識を持ってプロジェクトを進行できるよう設計した
今回の検証では、サステナビリティレポート制作を担当するサステナビリティ委員会のメンバー、取材対象となる社長へ、個別に検証の趣旨や「ailead」の機能、AIと人の役割分担を説明する機会を設け、関係者の意識合わせを行いました。
「フィードバック」機能を利用するには、60項目の設問と解答案からなる「カスタムプロンプト」の作成が必須となる。これを基に取材質問案を作成するとA4で6枚相当のボリュームとなり、今回の検証にとっては項目数が多すぎると感じた
「ailead」の特徴的な機能の1つが「フィードバック」機能ですが、この機能を利用するために必要なカスタムプロンプトの作成は解析結果を大きく左右する重要な工程です。「ailead」は営業商談での活用を想定して設計されており、仕様上、最低でも全4テーマ、テーマごとに3問、各問に5回答、計60項目を設定する必要があります。営業用途では合理的な設計かもしれませんが、広報・IR業務の用途によっては過剰な項目数となり、作成には多大な労力を要しました。
サステナビリティ委員会メンバーへの2025年版のテーマのヒアリング、生成AIを活用した2024年版レポートからの要点抽出や、他社のサステナビリティレポートのトレンド調査を基に60の設定項目を決定しました。カスタムプロンプトの作成、確認、修正、再確認、「ailead」への設定までには相応の工数とリードタイムが必要で、今回の検証では約3週間を要しています。
【検証2】取材実施:90分制限への対応
事前に作成したカスタムプロンプトをアレンジして取材質問案として使用しましたが、実際の取材では質問案の順番通りには進行しないことがありました。限られた時間の中で回答案のうち、何を優先し、何を割愛するかの判断が求められることから、インタビュアーの現場での判断力が求められました。
また、「ailead」の主要機能の利用には、録画データが90分以内という時間的制約があります。今回の取材はこの時間的制約を超過することも想定されたため、事前に3つの録画エージェントを時間差で設定し、途中で切り替えながら取材を進める工夫が必要でした。
録画データを90分以内に収めるため、取材では複数のエージェントを時間差で起動した。画面は分析結果の表示例で、左に録画映像、右に文字起こしやトピック抽出などの結果、下部に録画のタイムラインが表示される
【検証3】アウトプットの質:実用度の評価
文字起こし
文字起こしは話者の特定も含め、精度は高いものでした。業界の専門用語など一般的な文字起こしでは拾えないような用語などに少し手を加えることで、原稿のベースとして十分利用可能でした。
「文字起こし」機能の表示例。発言者ごとに段落を分けて表示され、話者識別の精度も高い。専門用語の認識にはやや難があるものの、軽微な修正のみで原稿のベースとして使用できる
トピック要約
長時間の取材や取材対象者の話が前後した場合でも、取材内容の要点をコンパクトにまとめるため、記事の見出しや構成を考える際に役立つ機能でした。
「トピック要約」機能の表示例。録画内容を自動的に複数のトピックに分類し、それぞれ要約する。長時間のインタビューでも全体像を把握しやすく、記事の見出しや構成を考える際に役立つ
フィードバック
項目数こそ多いものの、各項目に対するポイントや評価、改善提案は納得できる内容でした。
「フィードバック」機能では、事前設定したカスタムプロンプトと実際の発言内容を比較分析。想定通りに話せた項目、不足している項目を抽出して評価した上で、改善点を提示する。スピーチ原稿の修正や調整に活用できる
総評に加え、項目ごとに詳細な改善提案が得られる「フィードバック」機能。トピック単位で細かくブラッシュアップできるが、最低設定項目数が60あるため、求める成果物のボリュームによっては優先度を判断しながら活用する必要がある
メディアトレーニングへの適用可能性
メディアトレーニングでの利用も検証項目に加えましたが、現状の機能だけではメディアトレーニングとしての活用は限定的です。将来的に話す速度、抑揚、ペース配分、表情などの分析機能が追加されれば、より実用的なメディアトレーニングツールとなる可能性があります。
【検証4】見えてきた課題と限界
「トピック要約」と「抽出」については原稿作成時の参考やサステナビリティレポート全体のメッセージを確認するには十分なアウトプットでしたが、「フィードバック」については項目が60項目と多く、すべての改善点を反映するのは現実的ではありませんでした。また、前述の通り90分を超える取材となり3つのエージェントを使用した結果、アウトプットも3つに分割され、重複部分の調整作業が発生しました。
なお、今回の最終成果物はサステナビリティレポートの数ページの記事であったためこのような評価となりました。記者会見や動画撮影用の原稿を最終成果物とした利用であれば、評価が異なる可能性があります。
「ailead」に限った評価ではありませんが、生成AIによる文章は整った表現になるものの、発言者の「その人らしさ」や「言葉から伝わる熱量」が失われる印象がありました。これは、経営トップが発信する情報やメッセージに何を求めるかによって評価が分かれる点です。今回の検証では、サステナビリティ委員会のメンバーから、「生成AIを介して作成された文章は、雑誌編集長経験を持つ当社社長が日ごろから執筆している文章の下書きとしてはフィットしない印象がある」との評価を受けました。
そのほか、サステナビリティ委員会のメンバーからは、アウトプットに否定表現が多く含まれ社外向けメッセージとして使いづらい点や、経営トップのメッセージでは株価への影響やインサイダー情報の漏洩リスクがあるため人によるチェックが不可欠である点も指摘されました。
生成AIによる文章は整った表現になる一方、発言者の「その人らしさ」や熱量が失われる傾向がある。経営トップのメッセージでは、AIの出力をそのまま使うか、参考にしながら人が手を加えるか、求める成果物に応じた使い分けが必要となる
改善要望:2つの制約を解消できれば
以下のような機能改善・追加が実現すれば、営業支援ツールとして開発された「ailead」を広報・IR業務により適用しやすくなると考えられます。
録画時間の制限緩和
90分を超える取材やヒアリングは珍しくないため、時間的制約の解除は強く望まれます。また、この制限が解除できない場合でも、現在の録画時間や残り時間を視覚的に確認できるUIがあれば、取材中の時間管理が容易になります。
録画データが90分を超えていると表示される警告メッセージ。このメッセージが表示された場合は主要機能の多くが利用できなくなる。長時間インタビューでは複数エージェントの併用など、運用上の工夫が必要となる
カスタムプロンプトの設定項目数の柔軟性
現状の60という仕様上の最低設定項目数は、今回のような数ページの記事制作の場合には多すぎると感じました。カスタムプロンプトの設定項目数を、求める最終成果物に合わせて柔軟に変更できる仕様になれば、テーマやトピックを絞った情報やメッセージの発信が必要な場合など利用できる領域が広がります。
「フィードバック」機能に必須のカスタムプロンプト設定画面。最低60項目の入力が求められる。作成・確認・修正に約3週間を要した。営業用途では合理的だが、短い記事制作では項目数の柔軟な調整が望まれる
総合評価:導入を検討すべき企業とは
結論として、2025年8月現在のバージョンで「ailead」を広報・IR業務に導入する場合、用途を選べば有効だが、相応の工夫とノウハウが必要というのが今回の検証結果です。カスタムプロンプトの作成・設定、録画データの時間的制約への対応など、事前準備と運用上の配慮が求められます。
しかし、上記の機能改善が実現されれば、最終成果物の種類によっては高い利用価値が見込めます。中でも新製品発表やプレスリリースなどの情報発信には有効だと感じました。「ailead」を活用して直接担当者にヒアリングするだけで「トピック要約」「抽出」の機能から一次情報が得られるため、資料収集や調整、原稿作成業務の軽減につながる可能性があります。
経営トップや経営幹部のメッセージ発信は、発信者が何を重視するかによって活用方法が変わるでしょう。「自分の言葉で思いを伝えたい」という経営トップには、「ailead」の「トピック要約」「抽出」の機能のみでの最終成果物の作成は難しいかもしれません。一方、「必要なことが、適切に伝わればよい」と考える場合は、これらの機能のアウトプットを活用することで文章生成が容易になり、広報・IR担当者の業務負荷軽減にもつながるでしょう。
生成AI技術の進化を考えると、今後は「その人らしさ」や「言葉から伝わる熱量」を文章に盛り込む機能も実現する可能性があり、広報・IR業務におけるAI活用の幅はさらに広がると期待されます。
連載:【AIツールレビュー】企業コミュニケーションにおけるAI活用の可能性
- 1)膨大な公表資料から欲しい情報を収集し調査時間を大幅削減──企業分析プラットフォーム「KIJI」がもたらす価値
- 2)AI活用でIR業務はどこまで効率化できるか──「exaBase IRアシスタント」実証実験レポート
- 3)営業用AI「ailead」は広報・IR業務で使えるか? 検証で見えた「使える場面」と「3つの壁」
日経BPコンサルティング
「AI企業コミュニケーション タスクフォース」について
生成AI技術の戦略的活用を推進する組織横断プロジェクト。広報・IR部門における生成AI活用の調査・分析と、実証実験を通じたビジネス活用の検証を行い、企業コミュニケーションの高度化と新規事業機会の創出を目指している。2025年1月より調査・実証の2チーム体制で活動を展開。
コンテンツ本部ソリューション1部次長
AI企業コミュニケーション タスクフォース
菅原 研
海外旅行ガイドブック、IT・PC関連書籍の編集者を経て、2008年8月に日経BP企画(現・日経BPコンサルティング)に入社。日経BP社雑誌・Webサイト掲載の広告の編集・制作に加え、IT関連企業を中心に企業広報誌、周年事業、Webコンテンツ、カスタム出版書籍などのコンサルティング、企画、取材、編集、ディレクションなど多岐にわたるプロジェクトを担当。
※肩書きは記事公開時点のものです。